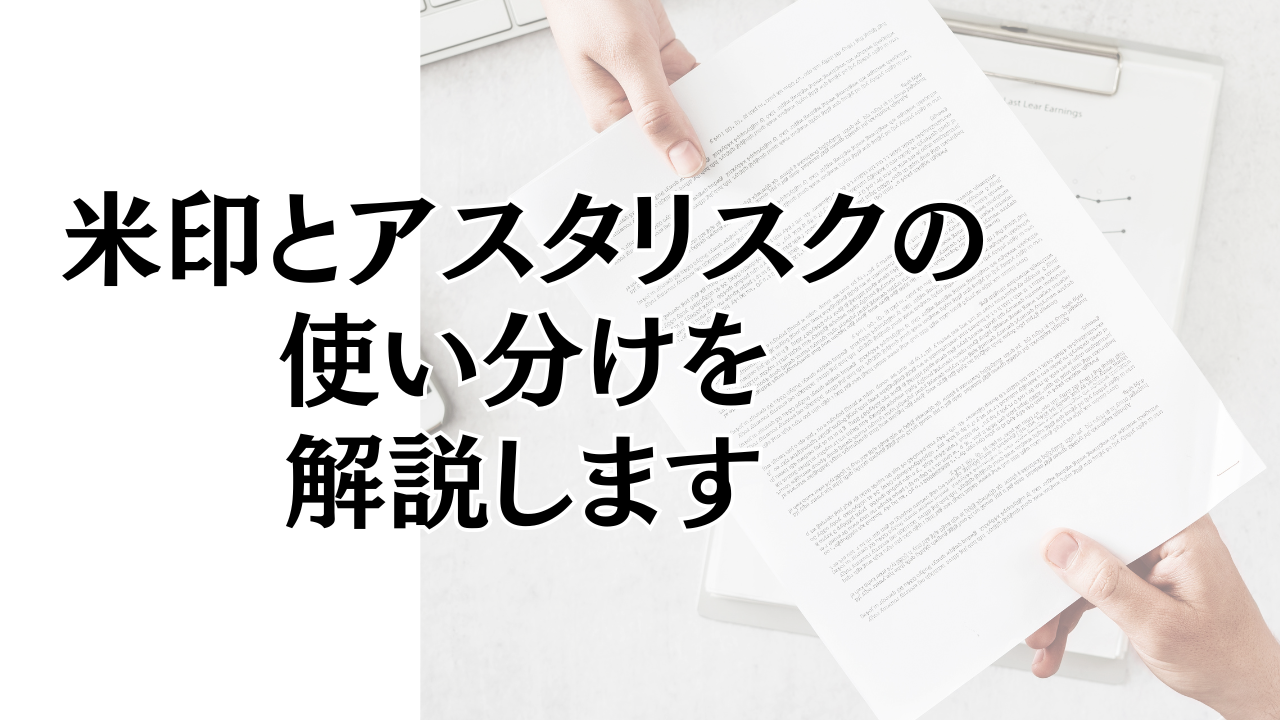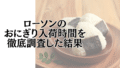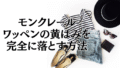米印(※)とアスタリスク(*)の違い
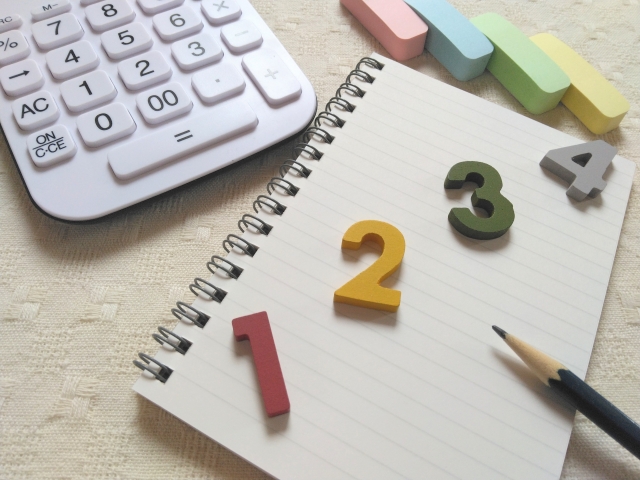
米印の正式名称と意味
米印(※)は、日本語における注記や補足情報を示す記号です。読み方は「こめじるし」で、主に文章中で注意喚起を促すために使用されます。特に契約書や案内文、商品説明などの公式文書において、本文に入りきらない補足事項や例外事項を示す際に活用されます。
また、米印は視覚的にも目立ちやすく、読者の注意を引く効果があるため、紙媒体やウェブ上の案内などでも広く利用されています。古くから日本語の文体に馴染みのある記号として、形式を問わず柔軟に使える点も特徴のひとつです。
アスタリスクの正式名称と意味
アスタリスク(*)は、主に欧米圏やグローバルな文書で使われる記号で、補足説明、脚注、注意喚起、さらには数学やプログラミングにおける特殊な記号としても用いられます。発音は「アスタリスク(asterisk)」で、語源はギリシャ語の「小さな星(asteriskos)」に由来します。
ビジネス文書や研究論文、マーケティング資料の中でも頻繁に登場し、多くの場合、文末やページ下に詳細を記す脚注との組み合わせで機能します。また、Markdown形式などの記述言語では、文字の強調(太字や斜体)にも利用されており、デジタル文書との相性も良い記号です。
米印とアスタリスクの使い分け
- 米印:
日本語文書や印刷物における注記、補足説明に最適。特に紙媒体の読みやすさを重視した文脈で使われる。 - アスタリスク:
英語表記、プログラムコード、国際的なドキュメントやオンライン文章での補足・強調用途に適している。 - 一般的に日本語には米印、英語にはアスタリスクを使うのが自然であり、それぞれの文化圏・表現スタイルに合わせた使い分けが重要となります。
米印の使い方

米印が必要な場面
- 商品やサービスに関する注意事項の記載
- 説明文における補足情報
- クーポン・キャンペーンの条件記載
- 保証・返品・交換などの条件を明示する際
- 例外事項や限定的な注意点を追加で説明したいとき
- 宣伝や広告の中で、読者の誤認を防ぐために補足情報を添える場面
特に、誤解を避けたい表現や、読者が勘違いしやすい文脈においては、米印を用いた補足によって文章全体の信頼性が向上します。
米印の注意書きの例
「この商品は※一部店舗では取り扱っていません。」
「※セール対象外の商品があります。」
「※キャンペーンは予告なく終了する場合があります。」
米印の使い方の具体例
- 本文中に「※」を記載し、ページ下部や文末に補足内容を明記して読者に分かりやすくする
- 見出しや項目の右側に米印をつけて、関連する補足を別途解説する
- 価格表示の後に「※」を添え、税込・税抜・送料別などの情報を追記
- イベント案内などで、特記事項や注意点を下段にまとめて示す際に活用
アスタリスクの使い方

アスタリスクが必要な場面
- 英文の脚注
- プログラミングや数式内での使用
- 強調や特定項目のマークアップ
アスタリスクの注意書きの例
“This plan includes free support.*”
“*Terms and conditions apply.”
アスタリスクの使い方の具体例
- 文末に*を付けて脚注で補足
- 数学での乗算記号(2 * 3)
- Markdownでの強調(bold)
米印をどこにつけるか

米印を使う場合の記載位置
- 補足情報が必要な語句や文末に付けることで、読み手に補足があることを直感的に伝えることができる
- 表や見出しに対して付加情報を記す際にも有効で、見出し直後に小さく米印を添えることで、視認性を損なわずに補足を促す
- 広告やチラシでは、価格や条件の後に小さく付記することで、詳細な条件を注記欄に誘導できる
- FAQ形式の文章や注釈が多い文書においては、視覚的に注目を集めやすいため、読者が情報の取りこぼしをしにくい位置に配置すると効果的
- 縦書き文書でも違和感なく使用できるため、レイアウトを崩さずに自然な流れで補足を挿入できる点も利点
文章における米印の使い方
- 「〇〇※詳細は下記参照」など、文中での使用によって読者の注意を即座に引き、必要な情報へ誘導する役割を果たします。
- 「※印の内容については後述します」といった使い方は、本文内で読者に先を読ませる効果もあり、読み進める動機づけにもなります。
- 「キャンペーン期間※変更の可能性あり」や「特別価格※条件付き」など、誤認を防ぎつつ補足情報を簡潔に伝えることができます。
- 文章中に複数の補足が必要な場合には、「※」「※※」「※※※」と段階的に記号を使い分けることで、読者が混乱せずに内容を追いやすくなります。
異なるコンテキストでの米印の位置
- チラシや広告では商品の横に配置されることが多く、「○○円※税込」や「送料無料※一部地域を除く」など、価格やサービスの条件説明に使われます。
- 契約書では注意書き項目に併記することで、契約内容の詳細や例外条項を示し、万一のトラブルや誤解を避ける手段として有効です。
- 書類やパンフレットの脚注部分で使用されることもあり、補足情報の一覧を視覚的に整理する目的でも重宝されます。
- ウェブサイトではリンクやツールチップに連動させ、マウスオーバー時に補足が表示される仕様などに使われることもあります。
アスタリスクをどこにつけるか

アスタリスクを使う場合の記載位置
- 補足対象の直後に付けることで、読み手に対して「詳細がある」という意図を即座に伝える役割を果たします。
- 箇条書きの中で特別な要素を示すときに活用することで、他の項目との差別化が容易になります。
- マーケティング資料や商品説明では、価格表示や割引条件の横にアスタリスクを付けて、補足説明や制限事項の案内に導く使い方が一般的です。
- 脚注や注釈を用いる文書では、文末や対象語句のすぐ後ろにアスタリスクを配置し、対応する注釈との対応関係を明確にします。
- プログラミングやIT系ドキュメントでは、定義や関数の補足説明のマーカーとして使われ、コード内での注釈や脚注的役割を果たします。
文章におけるアスタリスクの使い方
- “The product is free of charge.* Please refer to the footnote for details.”
- 「*付帯条件あり。詳細は下部に記載されています。」
- 「このキャンペーンは先着順で適用されます*(一部対象外あり)」
- 複数の補足を使う場合は「」「」「」と増やしていくことで、それぞれの注釈を区別しやすくする工夫が効果的です。
異なるコンテキストでのアスタリスクの位置
- コーディングでの定義や注釈としてのアスタリスクは、関数の引数における可変長リスト
(Pythonのargsなど)を示すほか、コメントブロック(例:/ 〜 */)を形成する記号としても用いられます。プログラミング言語によって意味合いが異なるものの、視認性が高く、補足的な説明や意図の明示に適しています。 - 学術論文や研究資料では、図表内の特定項目にアスタリスクを付けて統計的有意性や補足情報の存在を示すのが一般的で、読者に対して情報の重みや重要性を伝える手段として機能します。
- ビジネスプレゼンテーションでは、スライド内の数字や条件にアスタリスクを添えて、詳細説明を口頭または注釈で補足するという使い方も広く行われています。
米印の注意点

米印を使用する際の注意
- 多用しすぎると可読性が下がるため、使用は必要最低限に留め、重要な補足や誤解を招く恐れのある部分に限定するとよい。
- 複数の米印を使う場合は、補足の順序に注意する必要があり、「※」「※※」「※※※」のように段階的に示すことで、読者が内容を混同しないように配慮する。
- デザインやレイアウトとのバランスにも気を配り、本文の流れや読みやすさを損なわない配置が求められる。
- 米印の補足が離れた位置にある場合、補足先への明確な誘導(例:※詳細は下部参照)を入れると親切。
- デジタルコンテンツでは、米印にリンクを設定して補足内容にジャンプさせるなど、読者の利便性を高める工夫も効果的。
誤解を避けるための米印の使い方
- 明確に補足の内容がどの文言にかかるか示すことで、読み手が誤った解釈をすることを防げる。補足対象の語句の直後に米印を置くのが基本である。
- 同ページ内で完結させるのが理想で、ページをまたぐような補足は避けたほうがよい。どうしても別ページになる場合は、その旨を明示しておくとよい。
- 複数の補足が存在する場合は、それぞれに対応する注釈を読みやすく整理し、表やリスト形式にすることで理解を促進できる。
- ビジネスや公式文書においては、米印の使い方一つで信頼性や正確性に差が出るため、丁寧な構成が求められる。
米印の使用に関するFAQ
Q:米印は複数使ってもいいの?
A:可能です。
ただし、使用数が多すぎると文章が煩雑になり、読みづらくなる恐れがあります。補足情報が複数ある場合は、段階的に「※」「※※」「※※※」のように使い分け、注釈の順序を明確にするとよいでしょう。
また、読み手にとっての負担を軽減するために、補足内容が簡潔にまとまっていることも重要です。複雑な補足が必要な場合は、表形式や別記の脚注欄を設けるのも一つの方法です。
Q:米印の代わりに数字付き注釈でもよい?
A:はい、場合によっては数字のほうがより明確で視認性が高くなることがあります。
特に複数の注釈が混在する文書や、正式な報告書、学術論文などでは、1、2、3…のような数字付き注釈が好まれる傾向があります。
ただし、文のトーンや媒体の種類によって適切なスタイルが異なるため、読者層や文書の性質に応じて使い分けることが大切です。
「※」マークの入力方法と便利な使い方

文章の中でよく見かける「※(こめじるし)」マーク。
補足や注意書きに使われることが多いですが、実はとても便利な記号なんです。ここでは、入力方法と日常での使い方をご紹介します。
入力のしかた(パソコン・スマホ)
- Windows:「Shift」+「8」を押して変換すると「※」が出ます。
「きごう」「こめじるし」と入力してもOKです。 - Mac:「Option」+「Shift」+「8」。
配列が違う場合は「記号」一覧から探すのも◎。 - スマホ:「きごう」や「こめじるし」で変換、または記号ボタンから選択。
アプリによって場所が少し異なります。
こんなときに使うと便利!
- 料金や注意書きに
「1,000円※」と書いて、下に「※送料別」と添えるとわかりやすくなります。 - キャンペーンや特典の補足に
「※初回限定」「※一部店舗を除く」と添えるだけで丁寧な印象に。 - 文章をすっきり見せたいとき
「このサービスは無料※」→ 下に「※初回のみ」など。流れを崩さず説明できます。 - 複数の補足を整理したいとき
「※」「※※」と使い分けると親切。使いすぎは見づらくなるので2〜3個が目安です。
使うときのコツ
- 「※」は補足したい言葉のすぐ後ろにつける。
- 内容は短くシンプルに。長い補足は別段落に。
- 「※詳細は下部をご覧ください」など、誘導を添えるとさらに親切です。
「※」と番号(数字記号)の関係性について

文章の中で「※」を使う場面のひとつとして、数字(番号)との組み合わせがあります。
ここでは、「※」と番号をどう連動させるか、その意味や使い方のコツをお伝えします。
なぜ番号を使うのか?
「※」だけだと、複数の補足情報があるときにどれがどの文に対応するか分かりにくくなります。
そこで 番号(1、2、3…) を併用することで、補足同士の対応を明確にできます。
たとえば:
本商品は送料無料※
① 一部地域を除く
② 離島は別料金
このように、※→①②と対応させると、読者が「どの補足が本文のどこにかかるか」を直感的に読み取れるようになります。
番号付き補足にするときの書き方のコツ
- 本文に「※」を置く
補足をつけたい語句のすぐ後ろに「※」を置きます。 - 番号を振る
補足する内容それぞれに「①」「②」「③」…などの番号を振り、補足一覧と対応させます。 - 補足は見やすく並べる
番号順に箇条書きや縦並びで補足を記すと、読みやすくなります。 - 番号の使いすぎに注意
あまり多くの番号を並べると、かえって混乱のもとになることも。補足はできるだけ絞るのがコツです。
番号付き補足を使うメリット・注意点
- メリット
– 補足の対応関係がクリアになる
– 複数の補足を整理しやすくなる
– 見た目にも「どれが補足か」が分かりやすくなる - 注意点
– 補足の内容が長すぎると番号表示の意味が薄くなる
– 番号と本文の対応を間違えないように気をつける
– 読み手に負担がかからないよう、番号の数はほどほどに
※マークと関連記号・利用分野のつながり

「※(米印)」は、日本語の文章でよく使われる記号ですが、これと関係の深い記号や、それが使われる分野について知っておくと、より適切に使い分けることができます。
関連する記号たち
- アスタリスク(*)
欧文で注釈や脚注を示すときに使われる星型の記号。日本語の文章でも併用されることがありますが、意味やニュアンスが“補足・脚注”という点で米印と重なる場面があります。 - ダガー(†)・ダブルダガー(‡)
複数の注釈を区別したいとき、脚注で順序を示すために使われることがあります。米印・アスタリスクと一緒に使われることが多い記号です。 - その他の約物・記号
括弧、句読点、中黒(・)、波線(〜)、省略記号(…)など、文章を整える記号のグループ「約物(やくもの)」の中に属します。文章全体のリズムや意味構造を調える役割があります。
使われる分野・設置される場面
- 出版・印刷
書籍や雑誌、新聞などでは本文の補足説明や注釈に「※」を使うことが一般的です。編集段階で、本文をすっきり保ちつつ必要な情報を補助的に伝えるための道具として活用されます。 - ビジネス文書・契約書・資料
見積書や契約書、説明資料などで、条件・例外・注意事項を明示するために「※」や関連記号を使うと信頼性がアップします。 - Web・ブログ・SNS
オンライン記事やブログで「※」を使い、本文内や末尾で補足を示すスタイルが多く見られます。特にスマートフォン閲覧時には、読者にとって自然に読み進めやすい形で補足を入れることが好まれます。 - 学術論文・学会発表
日本語文献や和文論文では、脚注や引用に「※」「†」「‡」などを使うケースがあります。ただし、学術分野では定められた注記ルールがあるため、スタイルガイドを確認することが大切です。 - 法律・契約関連
条文内部や契約書の細かい条件・注釈に「※」を入れることで、読み手に対する説明責任を果たす手助けになります。
アスタリスクの注意点

アスタリスクを使用する際の注意
- 誤って計算記号(たとえば「乗算記号」など)やプログラム内の演算子としての用途と混同されないようにする必要があります。
特に文脈が曖昧な場合には、アスタリスクの意味が複数考えられるため、注意が求められます。 - 英文中では脚注番号や別の記号(たとえば†や‡など)と混在させると、読み手にとって意味が不明瞭になる可能性があります。
そのため、アスタリスクを使用する際は、その用途と役割が文中で明確になるよう心がけましょう。 - デザイン面でも、アスタリスクが周囲の記号と視覚的に似ているため、フォントやサイズの工夫により読み手に認識しやすくすることも一案です。
- また、アスタリスクに補足内容が存在することを明記する、または本文中で補足がある旨を導入することで、読者が混乱せずに情報を受け取ることができます。
誤解を避けるためのアスタリスクの使い方
- 使用場所に一貫性を持たせることは非常に重要です。文中での使用位置や脚注との対応関係にズレがあると、読者は正しい理解にたどり着けません。
見出しごとに使用法を変えるのではなく、文書全体を通じて統一したルールで使用することが推奨されます。 - 脚注が複数ある場合は、「※」「※※」「※※※」のように段階を設けるのが一般的です。
ただし、あまりに数が多くなると視認性が低下するため、一定数を超える場合には番号付き注釈に切り替えるのも有効な手段です。 - アスタリスクを使った補足には簡潔さも求められます。
補足が長くなる場合は、別途注釈欄や脚注の一覧を作成することで、主文の可読性を保つ工夫が求められます。 - また、読者がスマートフォンなど小さな画面で閲覧する場合を考慮し、アスタリスクのサイズや表示方法を工夫することも重要です。
アスタリスクの使用に関するFAQ
Q:アスタリスクは1個で十分?
A:補足情報が1つだけの場合は1個で十分ですが、脚注や注釈が複数ある場合は、数を増やして区別するのが一般的です。
「」「」「」というように段階的に増やすことで、それぞれの補足内容との対応関係が明確になります。
また、視認性を保つために、アスタリスクの数が多くなりすぎる場合には、別の記号や数字による脚注番号へ切り替えると効果的です。特にビジネス資料や学術文書では、注釈の整理が信頼性と読みやすさに直結するため、構成の一貫性を保つ工夫が求められます。
Q:IT用語の”wildcard”としての意味は?
A:アスタリスクはIT分野において”ワイルドカード”と呼ばれ、任意の文字列を意味する記号として使用されます。
たとえば、ファイル検索で「.txt」と指定すると、「任意の名前の.txtファイルすべて」を意味します。プログラミングでは、関数の引数に可変長データを渡す際(例:Pythonのargs)などにも使われ、柔軟な処理を実現する役割を果たしています。
また、検索機能やデータベースクエリなど多くの分野で広く応用されており、ITリテラシーの高い文脈では重要なシンボルとなっています。
アスタリスクの使い方で気をつけたいポイント
アスタリスク(*)は便利な記号ですが、使い方によっては誤解を招いたり、読みづらくなったりすることがあります。
特に文章中やビジネス文書では、控えめに・丁寧に使うことが大切です。
間違えやすいアスタリスクの使い方例
以下は、アスタリスクを使う際に気をつけたいケースです。
「少しやりすぎかも?」と思ったら、一度立ち止まって見直してみましょう。
- 複数の文にアスタリスクを連続して使う
文章のあちこちに「*」が並ぶと、どの補足がどの文に対応しているのか分かりづらくなります。
→ 対応する箇所が一目で分かるように、できるだけ一文にひとつまでにしましょう。 - 注釈の内容が長すぎる
アスタリスクで補足を入れるとき、説明を詰め込みすぎると読みづらくなります。
→ 長い補足は本文の下に「※」などを使ってまとめるほうがスッキリします。 - 強調と補足を混同して使う
SNSなどでは強調目的で「*重要*」のように使うこともありますが、正式な文書では避けたほうがよいです。
→ 強調したい場合は太字や下線を使う方が自然です。 - 他の記号と混在させる
「※」や「†」などの記号と併用すると、意味が重なってしまうことがあります。
→ 同じ文中では、補足記号はひとつに統一すると読みやすくなります。
米印とアスタリスクの便利な使い方

ビジネスにおける米印とアスタリスクの利点
- 注意事項を目立たせることでトラブル回避につながる。
特に誤解を防ぐための補足や例外事項の明示において、米印は紙の資料などで非常に視認性が高く、アスタリスクはWebやスライド資料などのデジタルコンテンツにおいて汎用性が高い。 - プレゼン資料での補足に役立つ。
口頭では補足しきれない説明や注意点を、視覚的に整理して伝える際にアスタリスクを用いることで、視線誘導がしやすくなる。米印はスライド内の図表や小さな注釈に使用されることで、見落としを防ぐ効果がある。 - メールや企画書などでも、要点を強調するためにアスタリスクを使えば読み手に注意を促しやすくなり、米印を使えばビジネス上の重要な制約事項や但し書きを明確に示せる。
- 社内資料・マニュアルなどでのルールや例外の記載にも便利。
社員教育や業務引継ぎの際に、米印とアスタリスクを使い分けることで、情報の階層や意味を視覚的に整理できる。
注意書きや補足としての利用法
- アスタリスクは複数行にまたがる補足に向く。
特にプレゼンテーション資料やマニュアルなどで、段落や長文の補足を脚注として追記する際に適しており、文書の構成を崩さずに詳細説明を追加できる。 - 米印は単純な追記・注意喚起に適する。
たとえば価格表記やキャンペーンの条件、対象外商品などを簡潔に伝えるときに有効で、視認性の高さから、読み飛ばしを防ぐ効果もある。 - 両者とも、読み手の理解を補助し、誤読や誤解を回避するためのツールとして有効であり、特に社外文書や販促資料では使い分けのセンスが問われる。
特定の状況での使い分けのヒント
- 書面:米印 / デジタル・英語:
アスタリスク 紙媒体では視覚的に目立つ米印が有効です。特に印刷された資料や案内文、パンフレットなどでは、アスタリスクよりも米印のほうが読者の注意を引きやすく、誤解を防ぐ効果があります。
一方で、ウェブサイトやPDFなどのデジタル文書では、アスタリスクを用いることで、脚注やポップアップといったインタラクティブな表現が可能となり、ユーザー体験を向上させる役割も果たします。 - 契約書:
両方を併用し、明確に使い分ける 契約書では米印を主に日本語部分の補足や例外規定の注釈として使い、英語で書かれた条項や補足説明にはアスタリスクを活用するのが効果的です。
また、1つの契約書内に日本語と英語の表記が混在する場合、それぞれの言語に対応した記号を使うことで、文書全体の整合性と読みやすさが保たれます。
さらに、米印とアスタリスクの使い分けを冒頭や凡例に明記しておくと、読者の混乱を防ぐ助けになります。
複数の※マークを使うときのコツ
文章中で補足がひとつだけなら「※」を一つ付けるだけで十分ですが、
いくつも注意点や条件を伝えたいときは、複数の「※」を使う場面も出てきます。
そんなときに気をつけたいポイントを見てみましょう。
- 補足の順番をそろえる
「※」「※※」「※※※」のように段階をつけて使うと、どの補足がどの文に対応しているかが分かりやすくなります。
ただし、数が多すぎると見づらくなるので、3つくらいまでにおさえるのがおすすめです。 - 本文との対応を明確にする
本文に「※」を付けたら、下に対応する注釈をしっかり用意しましょう。
読者が「どの※がどの説明かわからない…」とならないようにするのが大切です。 - 複数の記号を混ぜない
「※」「*」「†」などを同時に使うと混乱しやすくなります。
同じ記事内では、基本的にひとつの記号に統一するのが見やすいです。 - Webでは見た目も意識して
スマホで読む人が多いブログでは、補足を段落の下や脚注として配置すると読みやすくなります。
CSSなどで少し余白を入れるだけでも、ぐっと見やすくなりますよ。
※マークを上手に取り入れるコツ
「※(こめじるし)」は、ただの注釈記号と思われがちですが、
使い方を少し工夫するだけで、文章がぐっと読みやすく、印象よくなります。
ここでは、ブログや日常文に取り入れるときのちょっとしたコツをご紹介します。
- 読み手の「ひと息ポイント」をつくる
長い説明の途中に「※」を使って補足を入れると、読むリズムが整います。
たとえば「この商品は送料無料です※」と書き、下に「※一部地域を除く」と添えるだけで、自然な流れで情報を伝えられます。 - 本文をスッキリ見せる
注意書きをすべて本文に書くと、文章が重たく見えがちです。
そんなとき「※」を使って下にまとめれば、メインの文章をスッキリ見せつつ、
必要な情報もきちんと残せます。 - 柔らかい印象を与える
ビジネス文書などで「注:」「備考:」と書くよりも、「※」のほうがやわらかく、親しみのある印象を与えます。
ブログや案内文、商品説明などでは特に効果的です。 - 文末よりも自然に添える
文章の途中で「※」をさりげなく使うことで、補足が読者の目に入りやすく、わざとらしく見えません。
「後で説明します」よりも、すぐに補足できる点がメリットです。
米印とアスタリスクの英語での表現

米印の英語表記
- 米印には特定の国際的な名称は存在しませんが、英語圏では“reference mark”や“Japanese asterisk”という表現で説明されることがあります。
- また、英語の文献や資料では、米印を特別な脚注マークとして紹介する際に「special note symbol」や「annotative symbol」などの一般名詞が使われることもあります。
- UnicodeではU+203Bとして「REFERENCE MARK」として登録されており、日本語特有の注記記号として扱われています。
- 一部のフォントや欧文組版ソフトでは、米印が正しく表示されないこともあるため、英語圏の文書に取り入れる際は表示確認が必要です。
アスタリスクの英語表記
- Asterisk(アスタリスク)として広く認知されています。
- 用例:Terms apply、Limited offer、*Conditions subject to change
- 国際標準化された記号であり、文書作成、プログラミング、デザイン、統計など多様な分野で汎用的に使用されています。
- そのため、英語を母語とする環境ではアスタリスクの意味や使用意図が即座に理解されやすい特徴があります。
英語での使い方の違い
- 英文では脚注や補足にアスタリスクを使うのが一般的で、1つの文書に複数の補足がある場合は、「」「」「」のように階層的に使用されます。
- また、ビジネス文書や法律文書でもアスタリスクは頻繁に利用されており、契約条件や但し書きの導入に使われることが多いです。
- 一方、米印は日本語の文化的背景に根ざした記号であり、英語圏ではほとんど使われることはありません。
主に日本語の印刷物やウェブコンテンツにおいて、注意喚起や補足の役割を果たす記号として位置付けられています。
※と*のはじまりと由来

「※(こめじるし)」や「*(アスタリスク)」は、いまでは当たり前のように使われていますが、
それぞれに長い歴史と背景があります。
米印の由来
「※」の形は、もともと漢字の「米(こめ)」を崩したものといわれています。
昔の文書では、注意や補足を書き添えるときに「米」の字を簡略化して記号のように使っていたそうです。
その名残が今の「こめじるし」。日本独自の発展をとげた記号なんです。
アスタリスクの由来
「*(アスタリスク)」は、古代ギリシャ語の「asteriskos(小さな星)」が語源。
印刷技術が発達する前から、欧米では文章中の注釈や補足を示す「星のような印」として使われてきました。
星型のデザインがそのまま形として残り、いまも世界共通で親しまれています。
現代への広がり
日本では「※」が印刷物や契約書などの文書に使われ、
海外では「*」が学術書・メール・プログラムなど幅広く使われています。
どちらも「本文をわかりやすくするための印」であり、
長い年月をかけて、人の伝える工夫のひとつとして定着したと言えます。
※と*の見た目の違いとその印象

「※(こめじるし)」と「*(アスタリスク)」は、どちらも注釈や補足を示す記号として使われますが、見た目や印象には意外と違いがあります。
ここでは、その視覚的な特徴と使い分けにまつわるポイントを紹介します。
形状・デザインの違い
- ※(米印)
日本語独自の記号とされ、漢字の「米(こめ)」を簡略化したような図案がベースです。交差する線や点が組み合わさった複雑さがあり、文字の中に混じっても存在感があります。
※ JIS規格にも含まれる記号として、日本語文書で広く使われる特徴があります。 - *(アスタリスク)
星型をモチーフにした記号で、欧文文化圏で古くから使われてきました。「小さな星」を意味するギリシャ語 asteriskos に由来しています。
点線的・放射線状の線が語感的にも軽やかに見え、英字文章や脚注などに自然に馴染みます。
印象と読みやすさの違い
- 目立ち方
※はその複雑な形状ゆえ、和文の中でひときわ目に留まりやすいです。補足や注意を書き添える際、「ここに重要なことがあります」という視覚的サインとして機能しやすいとされています。
*はシンプルな線の交差で構成されるため、和文中でも控えめな印象を与えることがあります。 - 混在時の視線誘導
もし同じ文章内に※と*を混ぜて使うと、記号同士のデザイン差が視線を分散させてしまうことがあります。視覚的な統一性が失われる可能性があるため、できればどちらか一方に統一して使うのが安全です。
用途・文化背景との結びつき
- 日本語文書では、※が定番の注釈記号として定着しており、アスタリスクが使われる場面は限定的です。
特に印刷物や正式文書では、※のほうが使われることが多い傾向にあります。 - 一方で、英語や欧文主体の文書では*(アスタリスク)が脚注・注記の定番であり、互換的に使われることが少なくありません。
たとえば、和文を英訳する際には「※」を「*」に置き換えるケースもあります。
※と*の共通点と違い

「※(こめじるし)」と「*(アスタリスク)」は、ともに注釈や補足を示す記号として使われますが、その性格や使われ方には重なる部分もあれば異なる点もあります。
ここで、両者の“似ているところ”と“注意して区別したいところ”を見ていきましょう。
共通している点
- 補足・注釈のマークとして使われる
どちらも、本文に書ききれない説明や注意書きを示すための目印として用いられます。たとえば「この語句に補足があります」というサインとして活用できます。 - 本文と注釈を結びつける役割
本文中に記号を置き、そこから下部や脚注部分などに対応する補足を記す構造は、※も*も共通しています。 - 視覚的に目立たせられる記号
どちらも文字の中に混じっても目立つため、読者の注意を引きたい部分で使いやすい記号です。
相違点・使い分けたいポイント
| 項目 | ※(こめじるし) | *(アスタリスク) |
|---|---|---|
| 発祥/背景 | 日本語文化圏で育まれた記号。「米」の字を簡略化した流れを持つとの説もあります。 | ギリシャ語 “asteriskos(小さな星)” に由来。欧文文化で長く使われてきた星型の記号です。 |
| 用途の傾向 | 日本語文書・印刷物・注意書き・案内文などで日常的に使われることが多い | 脚注、学術文書、国際的文章などで使われることが多い(特定用途での慣例が強い) |
| 見た目の印象 | 線と点が組み合わさった複雑さがあり、和文内では強めに目立つ | 比較的線がシンプルで、和文中でも軽やかに感じられることが多い |
| 混用のリスク | 日本文脈で使うぶんには違和感が少ないが、英語文書などでは※をそのまま使うと理解されない可能性あり | 日本語文書で多用すると、読者に違和感を覚えられることがある |
| 異文化コミュニケーション時の扱い | 英語文書に翻訳する際、※は *(アスタリスク)に置き換えることが多い | 欧文圏では脚注記号として確立された使い方があるため、*を使うのが自然とされる場面が多い |