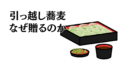X(Twitter)で興味深いツイートや画像を保存するためにスクリーンショットを撮った時、それが相手に知られてしまうのではないかと心配したことはありませんか?
この記事では、X(Twitter)でスクリーンショットを撮ることが相手に通知されるのか、また注意すべき点について解説します。また、著作権やプライバシーを保護しつつ、安全にX(Twitter)を使用するための情報を提供します。
- Xでスクリーンショットは本当に通知されるの?
- スクリーンショットに関する通知:X(Twitter)の現況
- 他SNSと比べるとどう違う?(Instagram・Snapchatなど)
- スクリーンショットのリスクと注意点
- スクリーンショットを安心して使うための5つのコツ
- DMでのスクショ事情:通知はある?注意点は?
- X(Twitter)で画像をダウンロードすると他のユーザーに通知されるのか?
- スマホとパソコンでのスクリーンショットの撮り方
- 2025年以降に注目したいスクショをめぐる動き
- スクリーンショットを安心して使うコツと代わりの方法
- 自分の投稿を守るためのスクショ対策
- 技術面から考えるスクショ通知機能の実現性
- スクショ以外で気づかれてしまう行動
- ポストをスクショすると表示される「X.com」のマークとは?
- まとめ
Xでスクリーンショットは本当に通知されるの?
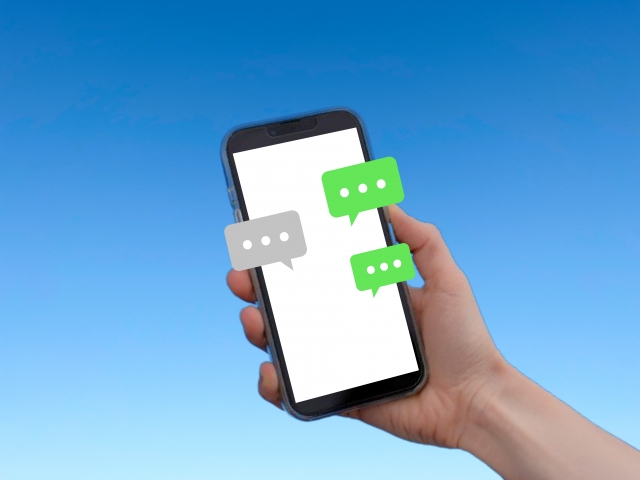
X(旧Twitter)で投稿を見ているとき、「スクショを撮ったら相手にバレるのかな?」と気になる方も多いですよね。
結論から言うと、現在のXにはスクリーンショットを撮っても通知が届く機能はありません。
そのため、スクショを撮っただけで相手に知られることは基本的にありません。
ただし、「絶対にバレない」とは言い切れない面もあります。
通知以外で“バレる”ことがあるケース
通知がなくても、以下のような場面ではスクリーンショットを撮ったことが気づかれることがあります。
- 投稿内容をそのまま他で使ってしまったとき
スクショをSNSやブログにアップした場合、投稿内容がそのままだと元の投稿者に気づかれることがあります。 - 画像の特徴で分かってしまうとき
文字の配置や背景の色合いなどが一致すると、「あれ?これ自分の投稿だ」と思われる可能性も。 - 撮影後の行動で察されることも
スクショを撮った直後に投稿したり、話題にしたりすると、相手が察することもあります。
今後の仕様変更にも注意
Xではこれまで何度も仕様が変わっており、今後も新しい機能が追加される可能性があります。
たとえば、Instagramではストーリーのスクショを通知するテストが行われたこともあるため、
将来的にXでも通知機能が導入される可能性はゼロではありません。
定期的にアプリの更新内容や公式の発表を確認しておくと安心です。
スクショを使うときのマナー
スクリーンショットを撮ること自体は問題ありませんが、次のような点に注意しておくとトラブルを防げます。
- 公開目的で使う場合は、投稿者の許可をとる
- どうしても引用したい場合は、出典を明記する
- 悪意ある使い方(晒しなど)はしない
スクリーンショットに関する通知:X(Twitter)の現況

X(Twitter)でスクリーンショットを撮った際に相手に通知が行くかどうか、多くのユーザーが疑問に思っています。過去には、通知されるという噂が流れたこともあります。
現在のところ、X(Twitter)ではスクリーンショットを撮っても通知はされません。以前、「フォロワーと共有できます」というメッセージが表示されたことがあり、それが原因で通知されるのではないかと不安に思う人もいましたが、そのような表示はもうされていません。
ただし、将来的にはX(Twitter)の仕様が変更され、通知機能が追加される可能性もあります。Instagramで一時的にストーリーのスクリーンショットが通知された例もあるため、X(Twitter)のアップデート情報には常に注意が必要です。
他SNSと比べるとどう違う?(Instagram・Snapchatなど)

X(旧Twitter)はスクリーンショットを撮っても通知が届きませんが、他のSNSではルールが少し違います。ここではInstagramとSnapchatの違いを簡単に紹介します。
Instagramの場合:基本は通知なし
Instagramでは、通常の投稿・ストーリー・リールをスクショしても通知はされません。
ただし、DM(ダイレクトメッセージ)で送られた「消える写真・動画」 をスクショした場合は、送信者に通知が届きます。
以前、ストーリーのスクショ通知がテストされたこともありますが、現在は実装されていません。
つまり、通常の使い方ではバレることはほとんどないと言えます。
Snapchatの場合:スクショ=通知される
Snapchatは特にプライバシー重視のSNSで、スクリーンショットを撮ると相手に通知が届く仕様です。
チャットやストーリーをスクショすると、「◯◯さんがスクリーンショットを撮りました」と表示されます。
設定で通知をオフにすることもできません。
スクリーンショットのリスクと注意点

現在、X(Twitter)でスクリーンショットが相手にバレることはありません。
これは、プラットフォームがユーザーのプライバシーを尊重し、スクリーンショットの情報を他人に伝えないためです。
ただし、通知がないからといって無断で内容を利用するのは避けるべきです。プライバシー侵害につながる行為は慎んでください。
スクリーンショットを安心して使うための5つのコツ

スクリーンショットはとても便利ですが、使い方を誤ると相手を不快にさせてしまうこともあります。
ここでは、安全に活用するための5つのポイントをご紹介します。
① 目的をはっきりさせる
スクショを撮る前に、「何のために保存したいのか」を明確にしておきましょう。
たとえば、情報をメモしておくため、証拠として残すためなど、自分の中で理由を整理しておくと安心です。
② 投稿者の許可をとる
他人の投稿やメッセージをスクショして公開する場合は、できるだけ相手に確認を取るのがマナーです。
無断で共有してしまうと、トラブルにつながることもあります。
③ 個人情報や背景に注意する
スクショした画像に、ユーザー名やアイコンなど個人が特定できる情報が含まれていないかチェックしましょう。
必要に応じてモザイクやトリミングをしてから使うのがおすすめです。
④ 出典を明記する
スクショを引用として使う場合は、「出典:○○(SNS名)」 のように出どころを明記しましょう。
相手のコンテンツを尊重する姿勢を見せることで、信頼性も高まります。
⑤ 仕様変更やルールを確認する
SNSはアップデートで機能が変わることがあります。
以前は通知されなかったスクショが、今後は通知される可能性もゼロではありません。
定期的にアプリの「お知らせ」や「利用規約」を確認しておくと安心です。
DMでのスクショ事情:通知はある?注意点は?

DM(ダイレクトメッセージ)内でスクリーンショットを撮ると、通知されるかどうか、また注意すべき点を整理しておきましょう。
X(旧Twitter)におけるDMスクショの現状
- 現行のXの仕様では、DM内のメッセージや画像をスクリーンショットしても、相手に通知されることはないとされています。
同様に、DM内の画像を保存(ダウンロード)しても通知は発生しません。
ただし、通知がないからといって無断転載や公開をしていいわけではありません。プライバシーやモラルを守ることは大切です。
他のSNSでのDMスクショ事情(Instagramなど)
- Instagramでは、通常のDMメッセージや画像をスクリーンショットしても通知は来ません。
ただし、消える(閲覧後に消える)写真・動画をDMで送った場合、それをスクリーンショットすると通知される仕様です。
また、Instagramの Vanish Mode(チャット中に消えるモード)でのスクショも、通知対象になります。
DMでスクショする際の注意ポイント
- コンテンツの種類を見極める
消える性質のメディア(写真・動画)が使われているかどうかを確認しておきましょう。 - スクショを撮った後の扱いに慎重になる
相手の許可なしに再配布したり公開したりするのはトラブルのもとです。 - 仕様変更に備える
SNSは機能を更新することがあるため、「通知の有無」が将来変わる可能性もあります。 - 画面操作や構図に気をつける
チャット相手の名前やアイコンなど、特定されやすい要素がそのまま映り込まないように配慮を。
DMでのスクリーンショットには、秘密性やプライバシーの部分が絡んできます。
無意識のうちに相手を不快にさせないように、使う前後の配慮を忘れないようにしましょう。
X(Twitter)で画像をダウンロードすると他のユーザーに通知されるのか?

X(Twitter)で画像をダウンロードした際に、その行為が他のユーザーに通知されるかどうかについての疑問は多くのユーザーが抱えています。
実際のところ、画像をダウンロードしても他のユーザーに通知されることはありません。ただし、ダウンロードした画像の取り扱いには注意が必要です。
1. DMを通じた画像のダウンロードとプライバシー
X(Twitter)でDMを通じて送られた画像をダウンロードしても、相手に通知されることはありません。
ただし、ダウンロードした画像を無断で使用するべきではありません。
特に、個人情報を含む可能性がある画像は慎重に扱うべきです。使用する前に適切な許可を得ることが望ましいです。
2. 画像の適切な管理
他人の画像をSNSで使用する場合、必ずその人の許可を得ること、およびプライバシーを尊重することが重要です。
画像を適切に管理することで、トラブルを避け、安心してSNSを使用できます。
3.画像から気づかれる可能性があるパターン
X(旧Twitter)では、画像をダウンロードしても通知が送られることはありません。
ただし、「まったく気づかれない」とは言い切れない場合もあります。
実は、画像の情報や使い方によって、相手に気づかれることがあるのです。
① 位置情報が残っている場合
スマホで撮影した画像には、撮影場所などの「位置情報(GPSデータ)」が含まれていることがあります。
そのまま保存や再投稿をすると、場所の一致などから元の投稿が特定される可能性があります。
画像を再利用する際は、位置情報を削除しておくと安心です。
② ユーザー名やアイコンが映り込んでいる場合
画像内に相手のユーザー名・アイコン・コメント欄が映っていると、投稿者がすぐに特定できてしまいます。
スクショや保存画像を使うときは、トリミング(切り抜き)やモザイク処理をしてから使うのがマナーです。
③ フォロー関係や共通のやり取りから気づかれる場合
たとえば、フォローしているユーザー同士のやり取りを保存・再投稿すると、周囲の共通フォロワーが気づくケースもあります。
「誰かの投稿を引用したようだ」と思われることがあるため、慎重に扱うのがおすすめです。
④ 投稿時間やコメントの一致
画像の投稿時間やコメントの内容が、オリジナル投稿と近いと、「これは私の画像では?」と気づかれることも。
保存した画像を他で使う場合は、日付・文面の一致にも注意しておきましょう。
4.画像検索から身元が分かってしまう可能性も
X(旧Twitter)では、画像をダウンロードしても相手に通知が届くことはありません。
ただし、「通知がない=安全」というわけではなく、画像検索(リバースサーチ)によって投稿元が特定されるリスクも存在します。
① Google画像検索などで一致が見つかることがある
保存した画像をGoogle画像検索や他のリバースサーチツールにかけると、同じ画像が投稿されている元ツイートやアカウントが表示されることがあります。
とくに、他サイトやSNSに同じ画像が掲載されている場合、投稿者の特定につながる可能性があります。
② 加工しても完全には防げない場合がある
一部のツールでは、トリミングや明るさを変えた画像でも類似検索でヒットすることがあります。
画像を少し加工しただけでは「別物」とは認識されず、同一人物が投稿した画像として見抜かれるケースもあるのです。
③ 背景や被写体から推測されるケースも
風景・部屋の様子・看板など、画像に写り込んだ要素から撮影場所や人物が特定されることもあります。
特に屋外で撮影した写真は、地域や建物の特徴から投稿者の居住エリアが推測されることもあるため注意が必要です。
④ 画像のメタデータにも注意
スマートフォンで撮影した写真には、「撮影日時」「位置情報」「機種情報」などのメタデータ(Exif情報)が含まれている場合があります。
そのまま保存・共有すると、これらのデータから撮影場所や時間が分かってしまうケースもあります。
SNSに投稿する前に、メタデータを削除しておくと安心です。
5.スクショ共有で思わぬところから気づかれることも
X(旧Twitter)で画像をダウンロードしても、直接的に通知が届くことはありません。
しかし、スクリーンショットを共有したことが“間接的にバレる”ケースがあります。
ここでは、その仕組みを少し詳しく見ていきましょう。
① スクショが別のユーザー経由で拡散される場合
誰かがあなたの投稿や画像をスクショし、それを他のSNSやグループチャットなどで共有した場合、その画像を本人が見つけてしまうことがあります。
とくにXでは拡散力が強いため、少しの共有でも意外と早く元の投稿者の目に届くことがあります。
② 画像の一部や文章内容から気づかれることも
スクショ画像にユーザー名やアイコン、投稿文などが残っていると、オリジナル投稿との一致で「自分のだ」と気づかれてしまうケースがあります。
小さな文字や背景の一部でも、フォロワーや知り合いが見れば分かってしまうことも少なくありません。
③ グループ内での共有から広がるパターン
LINEやDiscordなどのクローズドなグループで共有されたスクショが、メンバーの誰かからさらに転送・投稿されることもあります。
本人が意図していなくても、結果的に第三者の目に触れる可能性があります。
④ 拡散後に削除しても痕跡が残る場合
いったん共有・拡散されたスクショは、削除しても別の場所に残ってしまうことがあります。
とくに引用ポストやまとめサイトなどに転載されると、元の投稿を削除しても完全に消すのは難しくなります。
6.ツイートを他のSNSでシェアするときに気をつけたいこと
X(旧Twitter)の投稿をキャプチャしてInstagramやLINEなど、他のSNSで共有する方も多いですよね。
しかし、その行動が思わぬトラブルにつながることもあります。
ここでは、スクショやキャプチャをシェアする際の注意点をまとめました。
① ユーザー名やアイコンをそのまま載せない
スクショに投稿者のユーザー名・アイコン・リプ欄が写っていると、すぐに誰のツイートか分かってしまいます。
そのまま別SNSに載せると、無断転載や肖像権の問題になることもあるため、モザイクやトリミングで個人を特定できないようにしましょう。
② 投稿内容の一部を切り取ると誤解を招くことも
一部分だけを切り抜いて投稿すると、意図が変わって伝わる場合があります。
たとえば冗談の文脈が省かれた状態で広まると、誤解や炎上につながることも。
シェアする場合は、できるだけ文脈を保つか、「引用元あり」などの一言を添えると安心です。
③ 投稿者に許可をとるのがベスト
個人のツイートを他SNSに載せるときは、可能な範囲で投稿者にひとこと確認するのがおすすめです。
特に写真・イラスト・手書きなどのオリジナル作品は、無断転載と受け取られるリスクが高いです。
④ 他SNSでの拡散範囲に注意
Xよりも拡散力が強いSNS(例:TikTokやInstagramストーリーズなど)にシェアすると、想定外の人に見られることもあります。
「限定公開」「友達のみ」など、公開範囲を設定してから投稿することを意識しましょう。
⑤ 出典を明記してトラブルを防ぐ
どうしても紹介したいツイートは、スクショではなくツイートのURLを貼るのが安全です。
もし画像を使う場合は、「出典:X(旧Twitter)/@ユーザー名(敬称略)」と記載しておくと、誤解を防げます。
スマホとパソコンでのスクリーンショットの撮り方

スマホやパソコンを使用してX(Twitter)のスクリーンショットを撮る方法について説明します。
スマホでスクリーンショットを撮る方法
撮りたいツイートや画像をスマホに表示させて、以下のボタンを押してスクリーンショットを撮ります。
- iPhone:サイドボタンと音量上ボタンを同時に押す
- Android:電源ボタンと音量下ボタンを同時に押す フラッシュとシャッター音が鳴ったら、スクリーンショットの保存が完了します。
パソコンでスクリーンショットを撮る方法
- Windows:「Print Screen(PrtSc)」キーを押す
- Windows(範囲指定):「Windowsキー+Shift+S」を押す
- Mac:「Command+Shift+4」を押す 撮影後、画像を画像編集ソフトやペイントに貼り付けて保存します。
スクリーンショットの保存先と確認方法
- スマホでは、「写真」アプリや「ギャラリー」に保存されます。
- パソコンでは、通常「ピクチャ」フォルダに保存されます。
画像の扱いには注意が必要で、公開前には必ず許可を得ることが重要です。
2025年以降に注目したいスクショをめぐる動き

スクリーンショットを取り巻く環境は、利用者のプライバシー意識や技術の進化とともに少しずつ変化してきています。ここでは、2025年以降に特に気をつけておきたいポイントを紹介します。
通知機能の導入可能性と仕様変更の検討
現在のところ、X(旧Twitter)にはスクリーンショットを自動で通知する機能はありません。 ([WP 301 Redirects][1])
ただ、SNSプラットフォームでは過去にストーリーのスクリーンショット通知などの実験が行われたこともあるため、将来的に通知機能が導入される可能性はゼロとは言えません。
また、著作権保護や利用規約の見直しと併せて、スクショや保存・再利用に関する制限が強化される案が浮上する可能性も考えられます。
画像認証・リバースサーチ技術の進化による特定リスクの拡大
画像をもとに元の投稿や投稿者を特定する「リバースサーチ(逆画像検索)」技術は年々高性能化しています。
トリミングや色調補正を施した画像でも類似性を検出する機能が向上しており、スクショを加工しても完全に安全とは言えない状況が近づいています。
また、学術研究の分野でも、スクリーンショットに含まれる「ハンドル名・タイムスタンプ・テキスト情報」をもとに元投稿を検証する手法が検討されています。
つまり、キャプチャしたツイートの「誰がいつ投稿したか」「どの文面か」が手掛かりになり、間接的に投稿者を割り出す動きが強まる可能性があります。
利用規約・法規制の見直しと権利保護の強化
SNS事業者や法制度の側でも、著作権保護・プライバシー保護の観点から「スクショ・画像保存・再利用」に関するルールの見直しが起こる可能性があります。
たとえば、スクリーンショットを第三者へ無断で配布・転載した場合の制裁を明確化する条文が利用規約に追加されることも考えられます。
また、国ごとの法制度でも、デジタル著作物の扱いや「無断キャプチャ」に対する制約が強められる方向になるかもしれません。
リンク共有・シェアの誘導強化
最近のSNSでは、ツイートを「スクリーンショットでシェアする」よりも、「リンクをシェアしてアクセスさせる」よう誘導する設計が見られます。
これにより、スクショの拡散を抑えつつ、元の投稿元への誘導を促すという狙いがあるようです。
この流れは、スクショの代替として「リンクシェアがより主流になる」可能性を示唆しています。
スクリーンショットを安心して使うコツと代わりの方法

スクリーンショットはとても便利な機能ですが、使い方次第ではトラブルのもとになることもあります。
ここでは、安全に使うためのコツと、スクショを使わなくても情報を残せる代替方法をご紹介します。
① 個人情報が写っていないかチェックする
スクショを撮る前や公開前に、ユーザー名・アイコン・コメント内容など、個人を特定できる情報が写っていないか確認しましょう。
必要に応じてモザイクを入れたり、背景をトリミングすることで、相手のプライバシーを守ることができます。
② 公開目的なら出典を明記する
他人の投稿や画像を紹介したいときは、「出典:X(旧Twitter)」「引用元:@ユーザー名」 のように元情報を明記しておくのがマナーです。
これだけで誠実な印象になり、無断転載と思われにくくなります。
③ 許可をとれる場合は一言確認を
個人のツイートや写真を使いたい場合、できれば投稿者にひとことメッセージで確認をとるのが理想です。
小さな気づかいで、トラブルを防ぐだけでなく、気持ちのよい交流にもつながります。
④ SNSの「ブックマーク機能」を活用する
記録目的なら、スクショを撮らなくても保存できる方法があります。
Xには「ブックマーク」機能があり、他人のツイートを非公開で保存できます。
通知も送られないため、あとで見返す用途ならブックマークが最も安全です。
⑤ URLを共有する方法もおすすめ
ツイートを紹介したい場合は、スクショではなくURLリンクを共有する方法もあります。
元投稿に直接アクセスできるため、引用の誤解を防げるうえ、投稿者の意図もそのまま伝わります。
自分の投稿を守るためのスクショ対策

X(旧Twitter)では、残念ながら「スクショを防止する完全な方法」はまだ存在しません。
ただし、少しの工夫で“勝手に撮られにくくする”工夫はできます。
ここでは、自分の投稿を守るための具体的な対策を紹介します。
① 投稿内容を選ぶ
まずは「見られて困る内容」を投稿しないことが一番の防御です。
たとえば、顔写真・個人情報・勤務先など、身元につながる情報はなるべく避けるようにしましょう。
一度ネットに出た情報は、削除しても完全には消せない場合があります。
② 投稿範囲を制限する
Xには「鍵アカウント(非公開アカウント)」設定があります。
フォロワー以外にツイートを見せないようにすることで、第三者にスクショを撮られるリスクを大幅に減らせます。
フォローを承認制にして、信頼できる人だけが閲覧できる環境をつくるのがおすすめです。
③ 画像や写真に透かし(ウォーターマーク)を入れる
自分で撮影した写真やイラストなどは、小さく名前やアカウントIDを入れることで、無断使用を防ぐ効果があります。
完全に防ぐことはできませんが、再利用された際に“誰のものか”が分かる抑止力になります。
④ 投稿後すぐに削除・非公開にする
一時的に投稿したい場合は、「一定時間で削除」する運用もおすすめです。
たとえばお知らせや近況報告などは、見せたい人に伝わった段階で削除しておくと、スクショされる確率を下げられます。
⑤ 引用・転載された場合は通報を
もし自分の投稿が無断でスクショされ、他SNSなどに転載されているのを見つけた場合は、
Xの「報告・削除申請フォーム」から違反報告ができます。
悪意のある転載や誹謗中傷に発展している場合は、証拠を残しておくことも大切です。
技術面から考えるスクショ通知機能の実現性

「スクショしたら通知される仕組みって、技術的にできるの?」
そんな疑問を持つ方も多いですよね。
ここでは、技術的な観点から見たスクリーンショット通知機能の可能性について、やさしく解説します。
① スクリーンショットは“端末側の動作”である
スクショは、アプリではなくスマートフォンやPC本体が行う動作です。
そのため、アプリ(Xなど)単体では「ユーザーがスクショしたこと」を直接検知するのは難しい仕組みになっています。
通知機能を実現するには、OS(AndroidやiOS)側の協力が必要になります。
② 一部のアプリで通知できる理由
InstagramやSnapchatのDM機能では、「スクショを撮ったら通知される」仕組みが存在します。
これは、これらのアプリが一時的な画像表示モード(閲覧後に消える設計)を採用しているためです。
その状態では、アプリが画像を表示中に“撮影イベント”を監視できるようになっており、
スクショ操作を検知→通知する流れが可能になっています。
③ X(旧Twitter)で実装が難しい理由
Xは基本的に「すべての投稿が常時表示される仕様」のため、
ユーザーがどの画面でスクショを撮ったかを特定する仕組みが作りにくいという課題があります。
さらに、端末のスクショ機能は多様で、外部ツール・録画機能・仮想環境などを使えば検出を回避できてしまいます。
そのため、完全な通知機能を実装しても“抜け道”が多いのが現実です。
④ 技術的には可能だが、プライバシー面の懸念も
理論上は、アプリがOSのAPI(開発者向けの仕組み)を利用して、
「スクリーンショットが撮影された瞬間」を感知することは可能です。
ただし、これを常時監視する仕組みを導入すると、
ユーザーの操作履歴や端末情報を収集することになるため、プライバシー面での問題が大きくなります。
そのため、Xのような公開型SNSでは導入が慎重に検討される傾向があります。
⑤ 今後の展望
今後は、AI画像認識や投稿追跡技術の進化により、
「スクショ通知」ではなく“類似画像を自動検出して投稿者に通知する”ような仕組みが登場する可能性もあります。
すでにInstagramなどでは、AIが無断転載画像を自動検出する仕組みのテストが進んでおり、
Xでも将来的に「スクショそのものではなく、投稿の再利用を検出」する方向に発展するかもしれません。
スクショ以外で気づかれてしまう行動

「スクリーンショットを撮っても通知は行かない」と言われていますが、
実はスクショ以外の操作でも、相手に“気づかれてしまう”ことがあります。
ここでは、意外と知られていない「バレる可能性のある行動」を紹介します。
① DMの既読(既視)機能
X(旧Twitter)のDMでは、相手がメッセージを読んだかどうかが「既読マーク」で分かるようになっています。
この設定はオフにすることも可能ですが、オンのままだと、開いたタイミングが相手に伝わってしまうので注意が必要です。
気づかれたくない場合は、設定から「既読を表示しない」に変更しておきましょう。
② いいね・リポスト・ブックマークの挙動
投稿に「いいね」や「リポスト」をすると、当然相手に通知が届きます。
また、ブックマークは通知されない仕様ですが、もし引用ポストなどでコメントを添えてシェアした場合、
間接的に気づかれてしまうこともあります。
とくに過去投稿をまとめていいねする行為は、相手に「見返してる?」と思われやすいので注意です。
③ フォロー・フォロー解除の通知
フォローしたタイミングでは通知が届くため、気づかれやすい行動のひとつです。
ただし、フォロー解除の際は通知は届きません。
しかし、相手がフォロー整理アプリなどを使っていれば、フォロー解除も確認できる場合があります。
④ プロフィールや投稿を何度も閲覧する
Xでは、誰が自分のプロフィールを見たかは基本的にわかりません。
しかし、企業アカウントや一部の有料機能(X Premium)では、閲覧履歴や投稿の反応傾向を分析できるツールを利用している場合があります。
そのため、頻繁にチェックしていると「閲覧が多い相手」として検出されることも。
⑤ 画像の保存・共有の痕跡
画像を保存したり、他SNSで共有した場合、共有先で気づかれるケースがあります。
たとえば、LINEグループやInstagramストーリーズでの再利用などは、
共通フォロワーを通じて「この画像どこかで見たことある」と気づかれることがあります。
ポストをスクショすると表示される「X.com」のマークとは?

最近、X(旧Twitter)のポストをスクリーンショットすると、
画像の端に「X.com」のロゴやドメイン文字が自動で表示されることがあります。
これは不具合ではなく、X側が行っている公式の仕様変更によるものです。
① 「X.com」ロゴが入る理由
2023年のTwitterからXへのブランド移行以降、Xは投稿(ポスト)の出典を明確にする取り組みを進めています。
その一環として、アプリ内でポストをスクリーンショットした際に、
「この画像はXからの引用である」ということを示す目的で自動的に「X.com」ロゴが追加されるようになりました。
これにより、スクショが他SNSで拡散されても、どのプラットフォームからの内容かが一目でわかるようになっています。
② ロゴの位置と表示タイミング
- スクリーンショットを撮る際、画面下部や右下あたりに「X.com」という文字が小さく表示されることがあります。
- ただし、すべての端末・すべての投稿で必ず出るわけではなく、アプリのバージョンやOSによって表示の有無が異なるようです。
- Xの公式アプリから撮影した場合に出やすく、ブラウザ経由や外部ツールでのキャプチャでは表示されないケースもあります。
③ 削除・非表示にはできる?
現在のところ、「X.com」ロゴを非表示にする設定は提供されていません。
もしロゴを消したい場合は、
- 画像編集アプリでトリミング(切り抜き)する
- ロゴが写らない位置でキャプチャを撮る
といった工夫で対応するしかありません。
ただし、ロゴを残したまま投稿することで「引用元がXである」ことが伝わりやすくなるため、
マナー的にはそのまま残しておくのが望ましいといえます。
④ この機能が追加された背景
Xでは今後、投稿の出典表示や著作権表示の自動化を強化していく流れがあります。
スクショのロゴ表示もその一部で、
無断転載の防止や、AIによるポスト引用のトレース機能をサポートする意味合いがあると考えられています。
そのため、今後はスクショだけでなく、
シェア画像や埋め込みリンクにも「X.com」表記が自動追加される可能性があります。
まとめ

X(Twitter)で画像をダウンロードやスクリーンショットを撮っても、相手に通知されることはありません。しかし、画像の利用にはプライバシーへの配慮が必要です。
事前に許可を得ることで、安心してSNSを楽しむことができます。