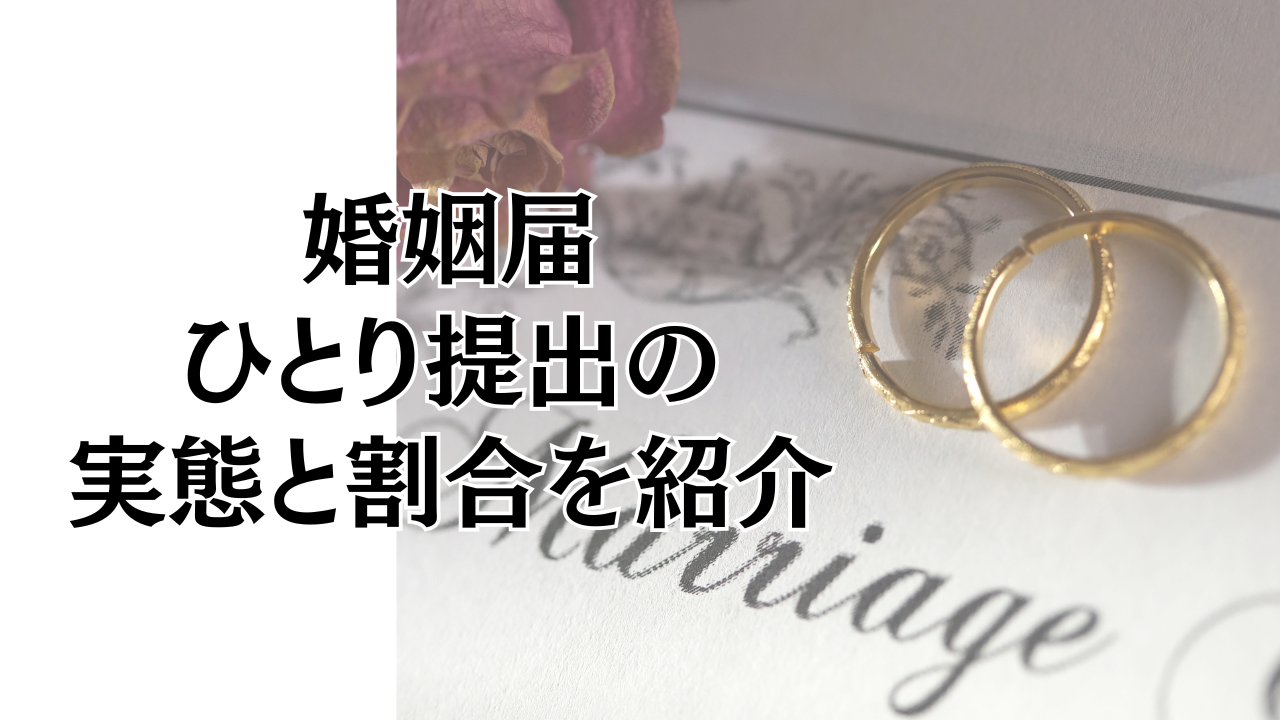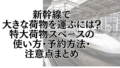婚姻届をひとりで出す割合とは?

婚姻届ひとり提出の現状
近年、婚姻届をひとりで提出するケースが以前よりも目立つようになっています。これは、共働きの増加やライフスタイルの多様化、結婚に対する価値観の変化などが背景にあります。実際、役所では「おひとりでの提出は珍しくありません」と案内されることもあり、社会的にも受け入れられつつあります。
法律上も、婚姻届の記入が正確であれば、提出はどちらか一方が行って問題ないとされています。そのため、現代においては「ふたり一緒に提出する」ことが前提ではなくなりつつあるのです。
ひとりで出すメリットとデメリット
メリットとしては、スケジュール調整の手間が省け、パートナーが仕事や他の事情で立ち会えない場合にも、円滑に手続きを進めることができます。また、混雑を避けて都合の良い時間帯に出しに行けるのも利点です。
デメリットとしては、人生の節目として記念に残したいという気持ちに応えづらいこと、また、万一書類に不備があった場合にその場で一緒に対応できないという実務的なリスクもあります。さらに、ひとりで行動することによる精神的な不安や孤独を感じる場合もあるでしょう。
婚姻届ひとり提出の割合や統計
全国的な統一データはないものの、自治体や民間調査会社によるアンケート調査では、婚姻届をひとりで提出した経験のある人はおおよそ全体の20〜30%にのぼるとされています。
また、SNSやブログなどで「ひとりで婚姻届を出してきた」という投稿も少なくなく、都市部を中心にその割合はさらに高まっている傾向があります。
コロナ禍を機に、役所の混雑回避やリモートワーク環境の広がりも相まって、単独提出のニーズが高まったという報告もあります。今後もこの流れは続くと予想され、提出スタイルの一つとして一般的な選択肢になると考えられます。
婚姻届を出す前に必要なもの

必要書類と印鑑の準備
婚姻届本体のほか、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、印鑑(シャチハタ不可)、そして本籍地が現在住んでいる場所と異なる場合には戸籍謄本も必要になります。
戸籍謄本は3か月以内に発行されたものが有効とされており、古いものでは受理されない可能性があるため、注意が必要です。
また、必要な書類が揃っていても、記載ミスや押印漏れがあると再提出になる場合があるため、提出前に念入りに確認することが重要です。加えて、印鑑については認印で問題ありませんが、必ず朱肉を使用するタイプのものを用意しましょう。念のため、パートナーの印鑑も持参しておくと安心です。
婚姻届の書き方と注意点
届出人欄、証人欄、住所・本籍欄などの記入欄には、誤字脱字がないように注意が必要です。漢字や旧字体の扱いにも注意が必要で、戸籍に登録されている正確な表記を確認しながら記入することが求められます。
また、記入は黒のボールペンや万年筆など、消えないインクを使うことが原則です。下書き用のコピーを活用して何度か練習し、本番の記入時には見直しを重ねながら丁寧に記入するよう心がけましょう。記入例や自治体の公式ガイドラインも参考にすると安心です。
証人の手配について考える
婚姻届には証人2名の署名と押印が必要です。証人は成人であれば親族や友人など、第三者であれば誰でも構いませんが、名前と住所、本籍、押印が必要です。署名と押印は自筆でなければならず、代筆は無効です。
遠方に住んでいる証人を頼む場合は、事前に郵送でやり取りするなどして準備しておきましょう。証人の記入欄が未記入で提出してしまうと、婚姻届は無効となるため、最後まで責任を持って確認することが大切です。
ひとりで婚姻届を出す方法

役所での手続きの流れ
窓口では、まず受付で婚姻届を提出し、担当者がその場で記載内容や添付書類の確認を行います。不備や漏れがなければ、受付印が押されて正式に受理されます。必要に応じて、受理証明書や婚姻届受理通知の発行を申請することも可能です。
提出は一人でも問題なく行えますが、書類にミスがある場合は再提出が必要になる可能性があるため、念のためボールペンや訂正印なども持参しておくと安心です。役所の担当者は丁寧に対応してくれることが多く、初めての人でもスムーズに手続きを終えることができます。
提出前にチェックすべき事項
婚姻届の提出において最も多いトラブルが「記入漏れ」です。特に、証人欄の署名・押印、本籍地の記入、日付の整合性などは見落としやすいポイントです。また、書類が濡れていたり、破損していたりすると受理されないこともあるため、丁寧な保管と持ち運びを心がけましょう。
自治体によっては、記入済みの婚姻届を事前にチェックしてくれるサービスを行っている場合もあるので、事前に役所へ確認しておくとより安心です。
戸籍謄本等、必須書類の取得方法
本籍地が現在住んでいる住所と異なる場合、戸籍謄本が必要になります。これは本籍地のある市区町村役場で取得する必要がありますが、最近では郵送請求や、マイナンバーカードと連携したオンライン請求が可能な自治体も増えています。
郵送請求の場合は、申請用紙・本人確認書類のコピー・定額小為替・返信用封筒を用意し、数日から1週間ほどの余裕をもって申請しましょう。オンライン申請であっても、郵送で届くまでに時間がかかることがあるため、婚姻届提出予定日より前に余裕を持って準備することが大切です。
婚姻届をひとりで出す理由

自立した結婚のスタイル
それぞれが自立した存在として結婚を選ぶカップルが増えています。恋愛や結婚においても、自分自身の価値観や生き方を大切にしたいという人が多くなっており、「ふたりで一緒に婚姻届を提出する」という従来のスタイルよりも、実質的な合意と信頼を重視する流れが見られます。
また、自立した関係性では、お互いの生活や仕事を尊重しながらパートナーシップを築く姿勢が求められ、それが婚姻届の提出にも反映されています。たとえひとりで提出する場合でも、それはパートナーとの信頼関係があるからこそ成り立つ選択肢と言えるでしょう。
寂しさや不安の克服
ひとりで婚姻届を提出する際には、「本当にこれでいいのか」「ちゃんと受理されるだろうか」といった不安や心細さを感じる人も少なくありません。
しかし、その不安を乗り越えることで、自分自身の強さや責任感を再確認できる機会にもなります。また、ひとりで役所に向かうその時間も、結婚という大きな決断をひとりの大人としてしっかり受け止めるための、かけがえのない時間になるかもしれません。こうした経験は、今後の夫婦生活においてもきっとプラスに働くでしょう。
パートナーとの状況による選択
遠距離恋愛中や、どちらかが海外赴任・単身赴任をしているケースでは、ふたりでの提出が物理的に難しいこともあります。また、医療従事者やサービス業など、勤務時間が不規則な職業に就いている場合、休みを合わせるのが困難なため、ひとりでの提出を選ぶことがあります。
こうした背景には、互いに状況を理解し合い、信頼をもって対応する柔軟なパートナーシップのあり方が見て取れます。形式にとらわれず、現実に即した選択をすることも、現代的な結婚のひとつの形です。
婚姻届提出後の流れ

受理のタイミングと注意点
婚姻届の提出後、書類に不備がなければ原則としてその日のうちに受理されます。受理されると、法的に婚姻が成立したことになり、戸籍にも反映される準備が始まります。
ただし、内容に不備や記入漏れがある場合は、即時受理されないケースもあるため注意が必要です。特に、本籍や証人欄の記載ミス、添付書類の不備などはよくある指摘事項です。
受理された証明が必要な場合は、「婚姻届受理証明書」を窓口で申請することができ、転居手続きや勤務先への提出などにも利用できます。また、深夜や休日に提出した場合は、仮受付となり、平日の開庁時間に本受付が行われる点にも留意しましょう。
戸籍の登録と生活への影響
婚姻が正式に受理されると、新しい戸籍が編成されます。一般的には夫または妻の本籍地を基準に新しい戸籍が作成され、その情報が住民票などの公的書類にも反映されていきます。
これにより、「配偶者」の続柄が登録されたり、婚姻日が記載されたりと、さまざまな公的記録が更新されます。新戸籍の内容は、発行された戸籍謄本で確認できます。
また、住民票や保険証、年金、税務関係など生活全般に影響が出るため、必要に応じて変更手続きを行う必要があります。特に名字が変わる場合は、行政手続きに時間がかかることがあるため、余裕を持ったスケジュールを意識しましょう。
結婚後の名前の変更について
婚姻により氏を変更する場合、婚姻届に記載された通りの氏が新たに適用されます。新姓を選んだ方は、各種名義変更を行う必要があり、銀行口座、クレジットカード、健康保険、運転免許証、パスポート、SNSやメールアドレスなどの情報更新も必要になります。
また、職場や学校などにも届け出が必要な場合があります。手続きは思いのほか多岐にわたるため、事前にチェックリストを作成しておくとスムーズです。変更手続きには、婚姻届受理証明書や新しい戸籍謄本が必要な場合が多いため、あらかじめ取得しておくと安心です。
ひとりで婚姻届を出す際の心配事

戸籍や住所の問題について
婚姻届が受理されると、新たな戸籍が編成されるため、戸籍上の住所や本籍地が変更になることがあります。
特に、夫婦で新たに本籍を設定した場合や、どちらかの本籍地に合わせた場合などには、従来の戸籍と内容が異なってくるため、事前にどちらの本籍地を選ぶかを相談しておくことが重要です。
また、婚姻に伴って住民票の住所も変更が必要になるケースがあり、引っ越しや同居を始める際には、住民異動届や世帯変更届など、他の行政手続きも併せて必要となる場合があります。転出・転入届のタイミングや、新しい住居での印鑑登録、マイナンバーの更新なども含めて、関連する手続きを事前に整理しておくと安心です。
不備があった場合の対応
婚姻届に不備があった場合、その場で訂正できることもありますが、記入内容によっては一旦受理されず、再提出となるケースもあります。
例えば、証人欄の漏れや記載内容の不一致、誤字脱字、押印忘れなどは頻出のミスです。こうした不備を防ぐためには、提出前に何度も確認を行い、可能であれば自治体の事前相談窓口で内容を確認してもらうのがおすすめです。
また、万が一に備えて予備の婚姻届を1枚持参する、訂正印や複数の筆記用具を準備するなど、臨機応変に対応できる準備をしておくと、当日も落ち着いて行動できます。
ひとりで出すことの心理的影響
婚姻届をひとりで出すことに対しては、心理的な抵抗や孤独感を覚える人も少なくありません。「本当にこれで大丈夫なのか」「誰にも祝福されずに進んでいるような気がする」といった不安に加え、役所の雰囲気に緊張してしまうこともあります。
しかし、そうした気持ちを乗り越えて提出することは、自分の人生の選択に責任を持つ大きな一歩とも言えるでしょう。事前にパートナーと気持ちを共有しておいたり、提出後にふたりでお祝いの食事をするなど、気持ちの切り替えや節目を設けることで、前向きな思い出として残すことができます。
事前に準備すること

婚姻届提出に必要な時間管理
婚姻届をスムーズに提出するためには、十分な時間管理が不可欠です。役所は平日午前中や昼休み時間帯が混雑しやすいため、なるべく空いている時間帯を選ぶと、待ち時間を大幅に短縮できます。
特に月初や月末、連休明けなどは来庁者が多く、婚姻届の受理にも時間がかかることがあります。また、書類の記入や最終チェックには予想以上に時間がかかる場合もあるため、予定の前後に余裕を持たせておくことが大切です。
移動時間や窓口での受付時間、番号札の取得などの流れも想定し、全体のスケジュールを立てておくと安心です。
役所の開庁日や時間について
役所の通常開庁時間は平日8時30分〜17時15分前後ですが、市区町村によっては夜間や休日にも時間外窓口を設けているところがあります。たとえば婚姻届や出生届、死亡届などは24時間365日受け付けている自治体もあり、窓口が閉まっている時間帯でも守衛室などで仮受付してもらえることがあります。
ただし、時間外提出は仮受付扱いとなり、後日正式な確認が行われるため、書類の不備があると受理までに時間がかかる可能性があります。事前に公式サイトで開庁日や時間、時間外対応の有無を確認しておくと安心です。
持参すべき書類の整理
婚姻届を提出する際は、当日に慌てないよう必要な書類をきちんと整理しておきましょう。婚姻届本体に加え、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、印鑑、戸籍謄本(必要な場合)などを事前に一式揃えておくことが重要です。
ファイルやクリアケースにまとめておくと、中身がバラバラにならず取り出しやすくなります。さらに、念のため予備の婚姻届や訂正印、筆記用具も持参しておくと、当日のトラブルにも冷静に対応できます。書類の並び順や提出の手順を確認しておけば、緊張せずに落ち着いて手続きを行えます。
婚姻届をひとりで出すケーススタディ

カップルの実体験紹介
「夫が海外赴任中だった」「急な転勤で日程が合わなかった」など、さまざまな事情から婚姻届をひとりで提出したというカップルの声が多く寄せられています。
例えば、ある女性は「夫が急に海外勤務になり、帰国の目処が立たなかったため、やむを得ず私ひとりで婚姻届を提出しました。でも、きちんと話し合って決めた上での行動だったので、不安よりも達成感が大きかった」と語っています。
また、別のケースでは「どちらかの仕事が忙しくて日程がどうしても合わず、せめて提出後に一緒にお祝いするという形に落ち着いた」という夫婦も。ひとりで提出することが寂しい、という気持ちを和らげるために、記念撮影やメッセージの交換など、ふたりの工夫によって前向きに受け止めている例もあります。
離婚歴のある人の婚姻届提出
再婚を機に婚姻届を提出する場合でも、ひとりで手続きすることは可能です。ただし、離婚届の処理状況が戸籍にきちんと反映されているかを事前に確認する必要があります。
戸籍の整備が済んでいないと、新たな婚姻届を受理できない場合があるため注意が必要です。さらに、姓の選択や子どもの親権に関する記載など、再婚ならではの注意点もあります。
再婚時には新たな戸籍を作成するか、既存の戸籍を使用するかの選択肢もあるため、家族構成や今後の手続きの利便性を考えて決めるとよいでしょう。自治体によっては再婚に関する相談窓口を設けているところもあるため、事前に問い合わせておくと安心です。
外国人との結婚の手続き
相手が外国籍の場合、日本国内で婚姻届を出す際には、追加の書類が必要になるケースが多くあります。具体的には、外国人側の「婚姻要件具備証明書」やパスポート、出生証明書などが求められます。
これらの書類は、大使館または領事館を通じて取得する必要があり、さらに日本語の翻訳文を添付することが一般的です。翻訳は自作でも可能ですが、正確性が問われるため、信頼できる翻訳業者に依頼することも検討するとよいでしょう。
また、国によっては先に母国での婚姻手続きを求められる場合や、日本での婚姻が自動的に有効とならないケースもあるため、各国の法律と手続きの違いについても十分な確認が必要です。
一般的な婚姻届の提出スタイル

ふたりで出す場合のメリット
婚姻届をふたりで一緒に提出することには、多くのメリットがあります。まず、結婚という人生の節目を共有する特別なイベントとして、記念撮影をしたり、役所の前で「ふたりの第一歩」を演出したりすることができます。
これにより、結婚の実感がより強くなり、思い出深い体験として残るでしょう。また、婚姻届の記載に不備があった場合にも、その場でふたりが協力して訂正や確認ができるため、再提出のリスクを減らすことができます。
さらに、お互いの両親や友人に報告しやすくなるなど、社会的な区切りとしても意義のある行動です。忙しい中でも「ふたりで行った」という事実が、のちのちの関係の支えとなることもあります。
近年の傾向と社会の変化
近年では、婚姻に対する価値観が急速に多様化しており、「必ずしも一緒に役所に行くべき」という固定観念にとらわれない結婚スタイルが広まっています。
共働き世帯の増加、遠距離恋愛、国際結婚など、ライフスタイルの変化に伴って、「自分たちらしい」結婚の形を選ぶカップルが増加中です。
また、SNSや動画サイトなどを通じて、他のカップルのさまざまな婚姻届提出スタイルが発信されることで、個性や創意工夫を取り入れる風潮も強まっています。こうした背景から、役所の側でも柔軟な対応が進みつつあり、時間外受付やフォトスポット設置といった取り組みを行う自治体も増えています。