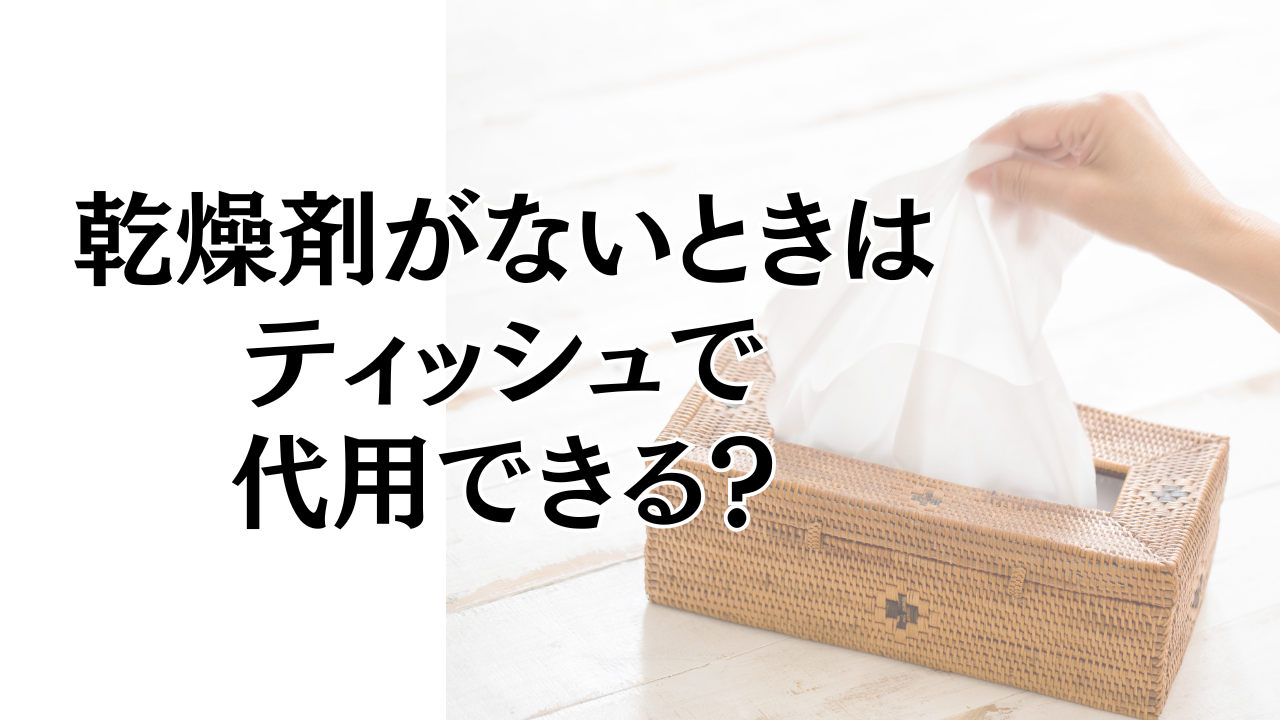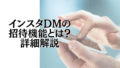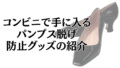食品や革製品、文房具など、湿気に弱いものは意外と身の回りにたくさんあります。保管状態を良好に保つためには、湿気対策が欠かせません。
乾燥剤があれば安心ですが、急に必要になって「今ない!」という場面もあるでしょう。そんなとき、身近なティッシュペーパーで代用できるとしたら、試してみたくなりませんか?
この記事では、乾燥剤の役割からティッシュで代替する際の注意点まで詳しく解説します。本当にティッシュで湿気対策ができるのか、一緒に見ていきましょう。
乾燥剤はどんな働きをするの?

乾燥剤の役割とは
乾燥剤は、湿度から大切なものを守るために使われます。周囲の水分を取り込むことで、腐敗やサビなどの劣化を防ぐ役目があります。
乾燥剤にはいくつかの種類があり、それぞれ用途に合わせて使い分けられています。
- シリカゲル:
透明の小さな粒状で、食品や精密機器のパッケージに多く使われています。湿気を吸うと色が変わるタイプもあり、交換の目安が分かりやすいです。 - クレイタイプ:
天然素材の粘土を使用しており、環境にやさしく価格もお手頃。 - 石灰系乾燥剤:
吸湿すると発熱する性質があるため取り扱いに注意が必要ですが、強力な吸湿力が魅力です。
乾燥剤が使われる主な場面
乾燥剤は家庭だけでなく、さまざまな場所で使われています。例えば:
- 食品の保存:
海苔や乾物などの風味と食感をキープ - 革製品の保管:
湿気によるカビやニオイを防ぐ - 精密機器の保護:
レンズやカメラの結露・故障防止 - 紙類の保存:
本や文書、紙製品のカビ対策 - 季節品の保管:
衣類やアルバムなどを湿気から守る
こうした場面で活躍する乾燥剤の働きを理解した上で、代用品としてのティッシュの可能性を考えてみましょう。
ティッシュで湿気を防ぐことはできる?

ティッシュに吸湿効果はある?
ティッシュは紙でできており、水分をある程度吸収する性質があります。これは紙に含まれるセルロースが水分と結びつきやすいためです。湿気の多い場所では、周囲の水分を一時的に吸い取ることができます。
ただし、乾燥剤のように湿度を一定に保つよう設計されているわけではないため、吸湿量には限りがあります。さらにティッシュは湿気を吸収すると全体に水分が広がりやすく、すぐに飽和してしまいます。
つまり、「少しの湿気を吸うことはできても、乾燥状態を長く維持することは難しい」といえます。
あくまで短期間の応急処置として
ティッシュを乾燥剤のように使う場合、その効果は一時的です。
例えば、旅行中に靴やカメラを一時的に湿気から守りたい場合など、短時間の使用には役立つでしょう。しかし、湿度が高い押入れや梅雨時の部屋などでは、すぐに効果が薄れてしまいます。
長く使うにはこまめな交換が必要であり、手間もかかります。そのため、ティッシュはあくまで「乾燥剤がないときの一時しのぎ」として使うのが現実的です。
本格的な湿気対策には、専用の乾燥剤を使うのが確実であることを覚えておきましょう。
ティッシュで作る簡単な除湿アイテム

重曹や炭を組み合わせて除湿力をアップ
ティッシュ×重曹
ティッシュに重曹を包んで、通気性のある袋や容器に入れてタンスや靴箱などに置くと、湿気だけでなくニオイの対策にも効果があります。
重曹はもともと消臭にも優れており、こもった臭いが気になる場所で特に活躍します。
また、湿気を吸って固まった重曹は掃除用として再利用できるので、無駄なく使えるのも嬉しいポイントです。
ティッシュ×備長炭
炭には無数の小さな孔があり、空気中の水分やニオイ成分を吸着する働きがあります。ティッシュで包んでおけば、粉が飛び散る心配もなく、設置もスマートにできます。
靴の中やクローゼット、衣装ケースなど、湿気と臭いの両方が気になる場所におすすめです。最近では、インテリアになじむ炭専用ケースも100円ショップで手軽に入手できます。
包み方次第で立派な即席除湿剤に
ティッシュを袋のように折り、中に重曹や炭を入れて包むだけで、簡易除湿剤が完成します。二重にしておくと破れにくくなり、使いやすさもアップします。
不織布の袋や小さなポーチに入れれば、見た目も整い、引き出しや靴の中など限られたスペースにもすっきり収まります。
また、布のハギレやお茶袋などで包み、リボンを結べば見た目もおしゃれで、ちょっとしたプレゼントにも最適です。家にあるもので気軽に作れるので、親子で一緒に作って楽しむのもおすすめです。
ティッシュを乾燥剤代わりに使うメリットと注意点

メリット:手軽でコスパもよく、応用が利く
- どの家庭にもあるため、急に必要になってもすぐに対応できる
- コンビニやスーパーで簡単に手に入り、特別な準備が不要
- 低コストで湿気対策ができるため、ちょっとした応急処置に便利
- 切ったり丸めたりと加工しやすく、使い方の幅も広い
- 余っているティッシュを有効活用できる点も魅力的
デメリット:効果は限定的で、こまめなチェックが必要
- 吸湿力は専用の乾燥剤には遠く及ばず、効果は一時的
- 湿度が高い環境ではすぐに飽和し、十分な効果を発揮できない
- こまめに交換が必要で、手間がかかる場合もある
- 見た目が簡素なため、見栄えを重視したい場所では使いづらい可能性がある
ティッシュはあくまで一時しのぎとしての活用が前提。状況に応じて上手に取り入れるのがポイントです。
ティッシュ以外でできる!身近な除湿対策

新聞紙やキッチンペーパーを使った除湿術
ティッシュよりも吸湿性に優れた素材として、新聞紙やキッチンペーパーも有効活用できます。
新聞紙は通気性が良く、水分を吸っても乾きやすいのが特長です。インクのニオイが気になる場合は、風通しのよい場所での使用がおすすめです。
キッチンペーパーは厚みがあり、吸水性も高いため、特に靴の中など湿りやすい場所に入れておくと効果的です。
使用アイデア:
- 食器棚や靴の中に敷く、または丸めて詰める
- 数枚重ねて折りたたみ、重曹や乾燥茶葉を包めば、除湿と消臭の両方に対応
- クローゼットや押入れでは、ハンガーに吊るして設置するのも◎。固定には安全ピンを使うと便利です
市販の除湿グッズを取り入れるのもおすすめ
100均やホームセンターでは、用途に応じた除湿グッズが多数そろっています。
主な製品例:
- シリカゲルや炭タイプの除湿剤は、繰り返し使えるものも多くコスパ良好
- 色が変わるタイプなら吸湿状況がひと目でわかり、交換の目安にもなります
- 珪藻土スティックやプレートはおしゃれなデザインも多く、玄関や棚にそのまま置いても違和感なし
- 小型除湿機やファンは電気代はかかるものの、部屋全体の湿度管理に役立ちます
場面に応じて、手軽な応急対策から本格的なアイテムまでうまく使い分けましょう。
ティッシュを除湿目的で使うときのよくある質問

Q. ティッシュでどのくらいの範囲をカバーできる?
A. ティッシュで吸収できる湿気の量は限られているため、広い場所には不向きです。タッパーや引き出し、靴の中など、密閉された小さな空間で使うのが適しています。
押し入れや部屋全体などには、ほかの除湿手段との併用が必要です。
Q. 交換のタイミングは?
A. 湿気の多い場所では数日で吸湿力が落ちることもあります。ティッシュがしっとりしてきたら交換の目安です。湿度が高い季節はこまめにチェックし、必要に応じて取り替えましょう。
使用場所によって吸湿スピードも変わるため、環境に合わせた管理が大切です。
Q. 使用済みのティッシュは再利用できる?
A. 一度湿気を吸ったティッシュは基本的に使い捨てです。見た目に問題がなくても内部に水分が残っていることがあり、再使用は臭いなどの原因になります。
再利用を考えるなら、再生可能なシリカゲルや珪藻土製の乾燥剤がおすすめです。
おわりに

乾燥剤が手元にないとき、ティッシュを使った簡易除湿は気軽に取り組める方法です。重曹や炭と組み合わせれば、消臭効果も期待できます。
ただし、長期間の湿気対策には限界があるため、状況によっては専用の乾燥剤を活用した方が安心です。ティッシュはあくまでも「その場しのぎ」として、うまく取り入れてみてください。
この記事が、ご家庭での除湿対策のヒントになれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。