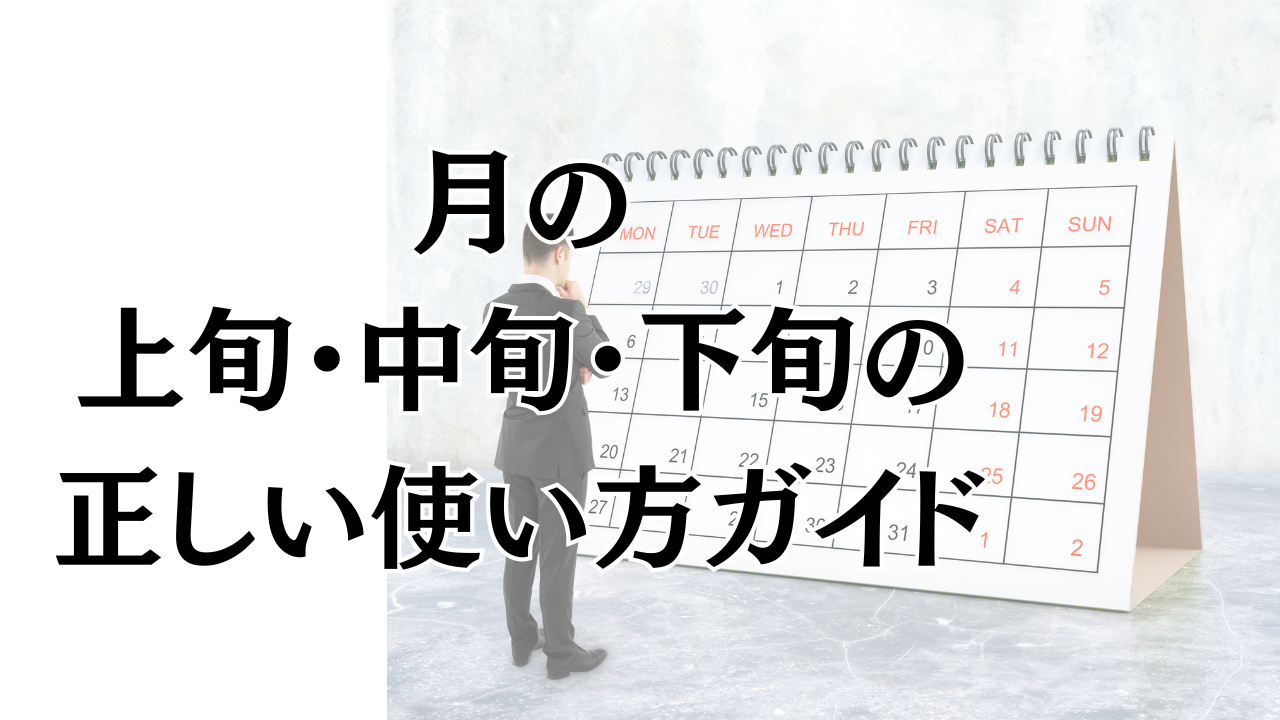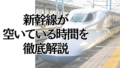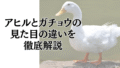上旬・中旬・下旬とは?

上旬・初旬の定義と期間
上旬とは、月の初めの約10日間を指します。一般的に1日から10日までの期間が上旬に該当します。この期間は新しい月の始まりとして、多くの人が新たな計画や目標を立てる時期でもあります。
特に、企業の業務や学校のスケジュールにおいて、上旬は重要なスタートのタイミングとなることが多いです。また、日本の伝統行事やイベントも月の上旬に行われることが多く、例えば1月上旬はお正月の行事が盛んに行われます。
一方で「初旬」という言葉も、ほぼ同じ意味で使われます。初旬もまた月の1日から10日ごろを指し、上旬と入れ替えて使っても誤りではありません。
ただし、一般的には「上旬」のほうが日常的に使われやすく、公的文書やビジネス文書などでも多く見られます。
上旬と初旬の違い
「上旬」と「初旬」はどちらも 月の1日から10日ごろ を指す言葉で、意味に大きな違いはありません。ただし、使われ方やニュアンスに少し違いがあります。
上旬
- 日常生活や公的文書、ビジネス文書などでよく使われる
- 安定した表現として幅広く浸透している
初旬
- 「月の初めごろ」というニュアンスを持ち、やや文学的・文章的な響きがある
- 公文書などではあまり使われないが、小説やコラムなどで用いられることが多い
そのため、普段の会話やビジネスの場では「上旬」を使い、少し柔らかい表現や文章的な表現をしたいときに「初旬」を選ぶと、より適切に使い分けることができます。
中旬の定義と期間
中旬は、月の真ん中の約10日間を指し、通常11日から20日までの期間を指します。この時期は、月の前半と後半をつなぐ重要なタイミングであり、ビジネスにおいても計画の進捗状況を確認することが多いです。
例えば、月の中旬には各種の報告書やミーティングが設定されることがあり、業務の整理や見直しが行われることが一般的です。
また、季節の変化が中旬ごろに顕著になることもあり、例えば6月中旬には梅雨が本格化し、9月中旬には秋の訪れを感じるようになります。
下旬の定義と期間
下旬とは、月の終わりの約10日間を指し、21日から月末までの期間を意味します。この時期は、月の締めくくりとして多くの業務が集中するため、特にビジネスシーンでは忙しい時期となることが多いです。
例えば、企業では月末の決算や売上報告が行われることが一般的で、計画の最終確認や締め切り対応が求められる時期です。また、年末には12月下旬に大掃除や年末の準備が行われ、新しい年を迎えるための準備期間ともなります。
「じゅん」の意味や語源、由来とは?
「じゅん(旬)」の意味
「旬(じゅん)」は、もともと 10日間をひと区切りとする期間 を表します。
現在では「上旬・中旬・下旬」という形で、月を三つに分けるときに使われています。
また、「食べ物の旬」という使い方では、その食材が 最もおいしく食べられる時期 を指す意味でも使われます。
語源と由来
漢字の成り立ち
「旬」は「十」と「日」を組み合わせた形で、「十日間」を意味する漢字です。
古代中国では暦の単位として「旬=十日」が使われており、そこから「一定の時期」を表す語になりました。
日本での定着
日本に伝わった際に、ひと月を「上旬・中旬・下旬」の三つに分ける表現として取り入れられました。
暦や農作業のサイクルと結びつき、自然に生活に根付いていったと考えられています。
「初旬」と「上旬」と「頭」の違い
「初旬」「上旬」「頭」はいずれも “月のはじめごろ” を指す言葉ですが、それぞれニュアンスや使われ方・範囲感に違いがあります。
以下で比較しながら整理してみましょう。
概念と範囲の違い
| 言葉 | 意味・範囲 | ニュアンス |
|---|---|---|
| 上旬(じょうじゅん) | 月の1日から10日までの10日間 | 月を三分割する表現として定着しており、比較的明確な期間を示す |
| 初旬(しょじゅん) | 本来は上旬と同義、1日〜10日あたり | 「月の初めごろ」「最初の時期」というやや曖昧な感覚を含むこともある |
| 頭(あたま、月頭) | 月の 1日〜5日あたり(もしくは数日間) | より “始まり” を強調する語感。ざっくりと「月の最初あたり」を指す使い方が多い |
たとえば、「8月の頭に〜」と言えば 1日〜5日あたり、「8月初旬に〜」/「8月上旬に〜」と言えば 1日〜10日あたりが指されるというイメージです。
用法の違いと使い分けのコツ
- 上旬 は、ビジネス文書やスケジュール案内などでよく使われ、比較的誤解が少ない表現として重宝されます。
- 初旬 は、意味的には上旬と重なることが多いですが、文脈によっては “月の初めごろ・最初の時期” といったよりゆるい期間を示すこともあります。
- 頭/月頭 は、話し言葉やカジュアルな表現で好まれることが多く、「最初あたり」「始まりの頃」のニュアンスを強く含みます。特に正確な10日区切りとはされず、柔軟に使われることがあります。
例文での比較
| 表現 | 例文 | 意味合い・印象 |
|---|---|---|
| 〜月頭 | 「5月頭に会いましょう」 | 5月1〜5日あたりをざっと示す |
| 〜月初旬 | 「5月初旬に発送します」 | 5月1〜10日あたり、最初の時期を指す |
| 〜月上旬 | 「5月上旬に開催予定です」 | 5月1〜10日あたり、スケジュール案内として明確性を伴う表現 |
ビジネスシーンでの使い方

上旬・中旬・下旬が使われるビジネスシーン
ビジネスメールや契約書、報告書、納期など、特定の日付を明確にしなくても相手に伝わりやすい場面で使用されます。
特に、プロジェクトの進行状況を報告する際や、会議のスケジュール調整などでは、具体的な日付を指定せずともおおよその時期を伝えることができるため、柔軟なコミュニケーションを可能にします。
例えば、取引先との商談の際に「○月上旬に企画書を提出いたします」と述べることで、相手に提出期限の目安を伝えることができます。
同様に、納期や納品予定についても「○月中旬に製品をお届け予定です」と伝えれば、詳細な日付の調整が不要になるため、業務の進行をスムーズにする効果があります。
ビジネスでの挨拶と時候の挨拶
ビジネス文書やフォーマルなメールでは、時候の挨拶として「○月上旬の候」「○月中旬の候」といった表現が用いられます。これにより、季節感を持たせつつ、相手に礼儀正しい印象を与えることができます。
例えば、取引先へのメールで「拝啓 ○月上旬の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます」と書き出せば、ビジネス文書としての格式を保ちながらスムーズに本題へ移行できます。
また、社内の報告書や通知文においても、時候の挨拶を取り入れることで、より丁寧な文章になります。
相手に合わせた使い方
社内文書や取引先への連絡では、「○月の上旬にお届け予定です」「○月の中旬には作業が完了する見込みです」といった表現が適切です。また、プロジェクトの進捗報告などでは「○月下旬には最終調整を行います」と伝えることで、スケジュール管理がしやすくなります。
さらに、社内の業務スケジュールを調整する際にも、これらの表現は有効です。例えば、上司への報告時に「○月の中旬には進捗状況をまとめます」と述べることで、上司に対して作業の目安を伝えることができます。
また、チーム内の共有事項として「○月下旬には最終確認を行いますので、準備をお願いします」と伝えれば、チーム全体の動きを統一しやすくなります。
このように、上旬・中旬・下旬の表現を効果的に使い分けることで、ビジネスの場面においてスムーズなやり取りが可能になります。
日付との関係・何日から何日まで?

具体的な日付での使い方
例えば、「1月上旬」と言えば1月1日から10日までを指し、「3月下旬」と言えば3月21日から31日までを意味します。これらの区分を使用することで、ビジネスや日常のスケジュール管理がより簡潔かつ効果的になります。特に、スケジュールの調整が必要な場面では、具体的な日付を指定するよりも柔軟な対応が可能になります。
また、文化的な行事やイベントの開催時期もこの区分に基づいて決められることが多いです。例えば、4月上旬には入学式が行われ、8月中旬にはお盆休みがあるなど、季節ごとのイベントとも密接に関連しています。
さらに、旅行や天候に関する予測にも役立ち、「12月下旬には雪が降る可能性が高い」などの表現が一般的です。
月末との関連性、違い
「月末」とは、通常25日以降の最終日までを指し、下旬とほぼ重なる概念です。ただし、下旬が21日から月末までを指すのに対し、月末はその月の最後の数日間を特に強調する際に使われます。
例えば、「3月下旬に商品を発送予定」と「3月月末に発送予定」とでは、後者の方がより具体的なタイミングを指していることが伝わります。
企業の決算や報告書の提出期限など、正確なスケジュール管理が求められる場面では、「月末」という表現を使うことでより明確な指示を示すことができます。また、従業員の給料の支払い日なども「月末」に設定されることが一般的です。
初旬・上旬・中旬・下旬の違い
「初旬」は上旬とほぼ同じ意味ですが、より曖昧な表現とされることがあります。一般的に、初旬は1日から10日頃を指しますが、文脈によっては多少のずれが生じることもあります。
例えば、公式な文書や契約書では「上旬」と表記することが推奨される一方で、日常会話やビジネスメールでは「初旬」の方が柔らかい印象を与えるため、適宜使い分けるとよいでしょう。
また、新聞やニュース記事などのメディアでは、「5月初旬にイベント開催予定」などの形で使用されることが多いです。
中旬と下旬に関しては、比較的明確な期間を指すため、特にビジネスの場面では具体的な予定を伝える際に便利です。例えば、「8月中旬に会議を予定している」と言えば、11日から20日頃を指すため、相手におおよそのタイミングを伝えることができます。
英語での表現、伝え方、フレーズ

上旬、中旬、下旬の英語訳
- 上旬:early (month)
- 中旬:mid (month)
- 下旬:late (month)
状況に応じた英語表現
「April early」「April mid」「April late」のように表現します。
英語での使い方の例
“The event will be held in early June.”
“The shipment is expected in mid September.”
“We plan to release the product in late December.”
英語での使い方の例、メールで使える例文
日本語の「上旬・中旬・下旬」を英語にするときは、直訳できる単語がないため 表現で工夫する必要 があります。ビジネスメールなどでは、以下のように表現すると自然です。
「上旬」を英語で表す例
「上旬」は early + 月名 を使うとわかりやすいです。
例文(メール)
・We are planning to release the new product in early May.
(新製品の発売は5月上旬を予定しています。)
・The meeting will be held in early October.
(会議は10月上旬に開催されます。)
「中旬」を英語で表す例
「中旬」は mid + 月名 が一般的です。
例文(メール)
・The documents will be available in mid June.
(書類は6月中旬にご利用いただけます。)
・Our office will move to a new location in mid September.
(弊社オフィスは9月中旬に移転予定です。)
「下旬」を英語で表す例
「下旬」は late + 月名 を使うのが自然です。
例文(メール)
・We expect to receive your reply in late July.
(ご返信は7月下旬にいただける予定です。)
・The new system will go live in late November.
(新システムは11月下旬に稼働予定です。)
補足:より具体的にしたい場合
- 「around the beginning of May(5月初めごろ)」
- 「toward the middle of June(6月半ばごろ)」
- 「by the end of August(8月末までに)」
といった表現を使えば、さらに正確さを持たせられます。
まとめ表:日本語と英語の対応
| 日本語 | 英語での表現 | ニュアンス |
|---|---|---|
| 上旬 | early + 月名 | 月の初めごろ(1〜10日) |
| 中旬 | mid + 月名 | 月の中ごろ(11〜20日) |
| 下旬 | late + 月名 | 月の終わりごろ(21〜31日) |
口語と文語の違い
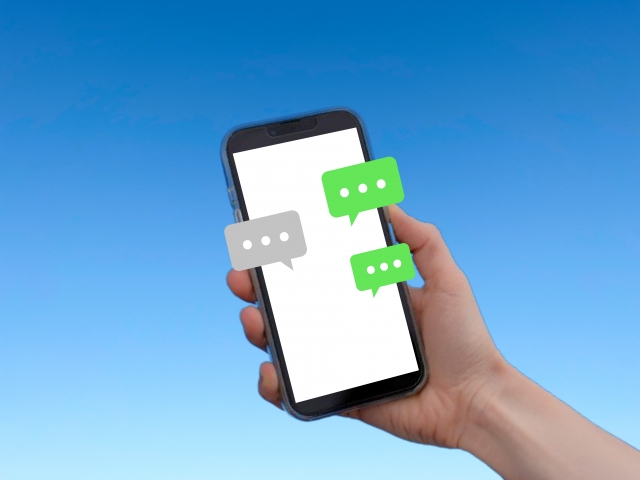
口語での使い方のポイント
日常会話では「来月の上旬には届くと思う」といった自然な言い回しが一般的です。口語では、相手に柔らかい印象を与えつつ、曖昧ながらも大体の時期を伝える役割を果たします。例えば、「来週の上旬には打ち合わせがあるかもしれない」など、ビジネスの場面でも使われることがあります。
また、カジュアルな場面では「たぶん今月の上旬に終わると思う」など、推測を交えた表現としても活用されます。
さらに、日常生活では友人との予定調整などで「今月の上旬なら時間があるよ」と伝えることで、大まかなスケジュール感を伝えることができます。特に、正確な日付を指定しない場合に便利な表現となります。
文書での使い方の基本
フォーマルな書面では「○月上旬に納品予定です」といった形で使われます。公的な文章やビジネスメールでは、相手に明確な期間を伝えるために、上旬・中旬・下旬といった表現がよく用いられます。
例えば、企業の公式な報告書や契約書では、「本プロジェクトの開始日は5月上旬を予定しております」のように記述し、正式なスケジュールとして提示されることがあります。
また、納期に関する書類や通知においても、「商品は9月上旬に発送いたします」と記載することで、受取人に正確な情報を伝えることができます。
さらに、公的機関からの発表文書やニュース記事でも、「新型設備の導入は10月上旬に完了する予定です」といった形で使用されることが多く、信頼性のある情報伝達の手段として用いられています。
状況に応じた使い分け
公式な文書では「○月上旬」とし、会話では「○月の初めごろ」と柔らかい表現を用います。特に、対外的なビジネス文書や公的な発表では、「○月上旬」が適切ですが、社内の会話やカジュアルなメールでは「○月の初めごろ」と表現することで、相手にとって分かりやすく、親しみやすい印象を与えることができます。
例えば、クライアントに対して正式な連絡をする場合、「○月上旬にご訪問いたします」とするのが望ましいですが、社内のミーティングの中では「○月の初めごろに報告できると思います」と伝える方が自然な印象を与えます。
また、状況によっては「○月上旬頃」「○月初旬」という表現も使われることがあり、より具体的なタイミングを示したい場合には「○月10日前後」などの形で補足することも可能です。このように、フォーマルとカジュアルの違いを意識しながら使い分けることで、適切なコミュニケーションが取れるようになります。
例文で学ぶ使い方

上旬の例文
4月上旬に入社式が行われます。新入社員が初めての職場に足を踏み入れ、新たな一歩を踏み出す重要な時期です。
7月上旬に梅雨明けの発表がありました。この時期から本格的な夏の暑さが始まり、夏休みの計画を立てる人も増えてきます。
1月上旬は初詣に多くの人が訪れる時期です。神社や寺院では新年を迎えた人々で賑わいます。
中旬の例文
5月中旬に新商品の発表があります。多くの企業が新年度の動向を踏まえた製品を発表し、市場に影響を与えます。
8月中旬には夏休みが終わります。学生たちは宿題の追い込みに入り、社会人もお盆休みを終えて業務に戻る時期です。
11月中旬には紅葉が見頃を迎え、多くの観光地で紅葉狩りが楽しめます。京都や奈良では観光客で賑わいます。
下旬の例文
10月下旬に紅葉が見頃になります。紅葉が深まり、山々が鮮やかな色彩に染まる時期です。
12月下旬にクリスマスイベントが開催されます。各地でイルミネーションやクリスマスマーケットが開かれ、賑やかな雰囲気が漂います。
3月下旬には桜の開花が始まり、花見シーズンの到来を告げます。多くの人が公園や名所で桜を楽しみます。
ランキング形式で見る使い方

上旬の使い方ランキング
- 納期の説明:「○月上旬に納品予定です」
- 行事の告知:「○月上旬にイベントがあります」
- 訪問の予定:「○月上旬にお伺いします」
中旬の使い方ランキング
- 予定の調整:「○月中旬が都合が良いです」
- 新製品の発売:「○月中旬に新モデルが出ます」
- 出張の計画:「○月中旬に海外出張があります」
下旬の使い方ランキング
- 目標の設定:「○月下旬までに完了させます」
- 季節の変わり目:「○月下旬から寒くなります」
- 年末年始の準備:「12月下旬に帰省します」
上旬・初旬・中旬・下旬に似た意味の単語、言い換え

「上旬・初旬・中旬・下旬」は、月を10日ごとに区切るときに使われる便利な言葉ですが、日常会話やビジネス文書では、似た意味を持つ 言い換え表現 が使われることもあります。
ニュアンスの違いを知っておくと、より自然に文章が書けます。
上旬・初旬の言い換え
・月初(げっしょ)
→ 「月の初め」を意味し、ビジネスメールや公的文書でもよく使われます。
例:「5月月初に会議を予定しています」
・頭(あたま)/月頭(つきがしら)
→ 口語的な表現で、1日〜5日あたりを指すことが多いです。
例:「7月の頭に旅行へ行く予定です」
中旬の言い換え
・半ば(なかば)
→ 「月の中ごろ」を意味し、日常会話から文章まで幅広く使われます。
例:「6月半ばに引っ越しします」
・月半ば(つきなかば)
→ より明確に「月の中間」を示す言葉。やや改まった印象。
例:「10月月半ばに工事が完了します」
下旬の言い換え
・月末(げつまつ)
→ 「月の終わり」を意味する一般的な表現。正確には“下旬”よりさらに終わりに近いニュアンス。
例:「9月月末に締め切りがあります」
・終盤(しゅうばん)
→ 「物事の終わりに近い時期」を表す語で、月に限らず幅広く使えます。
例:「8月終盤はイベントが多いです」
カジュアル表現とビジネス表現の違い
| 区分 | カジュアルに使える表現 | ビジネス文書向け表現 |
|---|---|---|
| 上旬・初旬 | 頭、月頭 | 月初、上旬 |
| 中旬 | 半ば | 月半ば、中旬 |
| 下旬 | 終盤 | 月末、下旬 |
よくある質問と回答

上旬・中旬・下旬に関する質問
Q: 「初旬」と「上旬」の違いは何ですか?
A: ほぼ同じ意味ですが、「初旬」はより柔らかい印象を与えることがあります。また、「上旬」はビジネス文書などの公式な場面で使用されることが多く、よりフォーマルな印象を持ちます。
一方、「初旬」は日常会話やカジュアルな文書で使われることが多く、柔軟なニュアンスを持つ表現として使われます。
例えば、ビジネスの場面では「4月上旬に納品予定です」と表現する方が適切ですが、日常の会話では「4月初旬ごろに行けるかも」といった使い方が自然です。
使い方に関する疑問
Q: ビジネス文書で「上旬・中旬・下旬」はどこまで正確に使うべきですか?
A: 相手に分かりやすい表現を心がけ、誤解を招かないよう注意しましょう。例えば、契約書や正式な報告書では「○月上旬」といった表現が好まれますが、具体的な日付を指定することでより明確に伝えることができます。「○月上旬(1日〜10日)に納品予定」と記載することで、より相手が誤解しにくくなります。
また、社内の業務連絡などでは、やや柔らかく「○月のはじめごろ」と表現することも可能ですが、フォーマルな文書では「○月上旬」と記載するのが一般的です。
注意点とアドバイス
上旬・中旬・下旬の期間は厳密に決まっているわけではないため、状況に応じて使い分けることが大切です。ビジネス文書ではより正確な期間を示すよう努めましょう。
口語では「○月のはじめごろ」「○月の半ば」「○月の終わりごろ」と柔らかい表現も可能です。特に、親しい関係性の中での会話や、ビジネスの場面でも非公式なやり取りでは、こうした言い回しの方がスムーズに伝わることがあります。
特に締切や納期に関する会話では、「上旬」だけではなく具体的な日付も併記することで、相手の認識を統一しやすくなります。
このように、フォーマルとカジュアルの使い分けを意識しながら、「上旬・中旬・下旬」を適切に活用しましょう。
このガイドを活用して、正しい表現を身につけましょう!